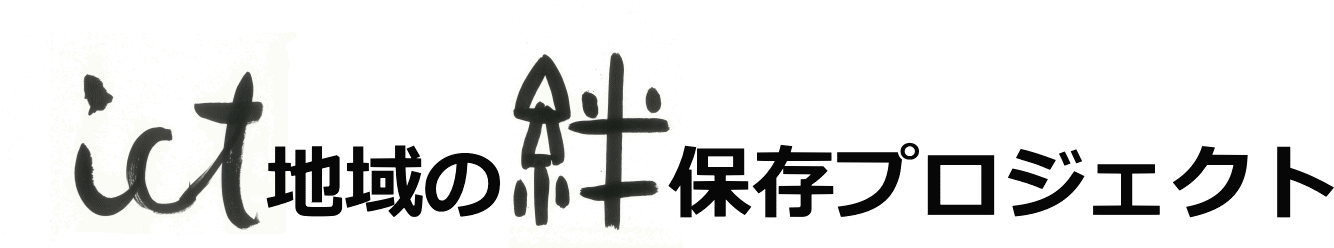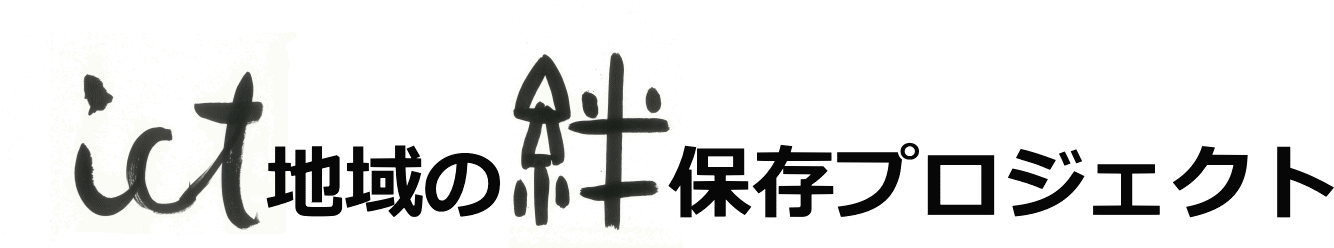川島 弘 40代 男性
かわしま歯科医院
(平成26年10月17日かわしま歯科医院にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
あの日は2時から診療が始まりまして、3名の患者さんがいました。皆、中に入って治療中だったのですが、揺れが今までにない位すごい大きかったし、宮城県沖地震も体験しているんですけどそれよりも大きいと思いました。ユニット全部起こして椅子から皆さん降ろし、しゃがんでもらい揺れが収まるまで待ってもらいました。物がけっこう倒れ、今まで地震来てもそんな倒れたりカルテが散乱することはなかったんですけど、これは尋常な揺れじゃないなと思いました。患者さん3名いたので、2名の方は自宅が心配だということですぐ帰宅していただきました。1名は一人暮らしのおばあさんで心細いから落ち着くまでここで一緒にいさせて下さいってことだったので、電気も消えちゃったので待合室にみんなで集まり、ラジオをずっと聞いて待機してました。津波が来るという無線はならなかったと思うんですよ。まさか津波が来るとは全然思ってもなかったので、外に出て隣近所の方とお話していたら車も渋滞で進まないし、家で落ち着くまでみんなでいようかと中に戻りました。
30分くらいして外が騒がしくなってきたんですよ。「何かおかしいな」と思って、出て聞きに行ったら「津波が来るみたいだから小学校にすぐ逃げて下さい」という話を聞きました。あわてて中に戻って半そでの白衣だったので防寒のコートを着て、スタッフにもコートを着させて、患者さんのおばあさんを背負って学校まで走って行きました。学校に行って、そのまま体育館に入ろうと思ったんですよ。そしたら1階じゃ駄目だから、2階より上に上がって下さいということでした。校舎に入ってそこから10分もたたないくらいですかね、「わあー」と外から声が聞こえてきたので「なんだろう?」と思って外見たら、もう津波が来て車が全部流されて行くのが見えたので、これはただごとじゃないなと思いました。小学校に水は来ているんですけど、自分の診療所は大丈夫だろうと頭の中で感覚だけはずっと残って、夢なのかなみたいな感じでその日は小学校で一夜を明かしました。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
【質問】これから震災時に口のケアはこうしようとか、今まで我々も考えてこなかったようなところを考えるようになってきているのかなと思うんですけど、歯科医さんの立場からはどうですか?
震災あってみて、歯磨きできないという人がけっこういるのが多かったので、震災後集めて小学校に歯ブラシとか何個か持って行ったんです。その辺、在庫とか置いておければ一番いいのかなと思います。シートで拭くのも応急にはなりますけど、やらないよりは全然いいです。ガーゼだと目が粗いのでけっこう汚れが取れるので、そういうのを代替して使ってもらうっていうのも広めて行ければいいのかなと。そういうやり方ありますよとわかれば、歯ブラシなくても口のケアできるので。
【質問】先生ご自身が震災後これは自分の中の変化かなとか、仕事に対して自分はこういうところが変わったなとかいうところがございますか?
仕事は震災前とスタンスはそんな変わってないと思うんですよ。ただ生活の方は、前は自分の好きな物、趣味の物であったりそういうのにお金かけたりしてたんですけど、今は質素になったというか、車も震災で流れて無くなって中古買ったんですけど今もそれ乗っているんですよ。前だったらすぐにでも新しいのを買ってたんでしょうけど、そういう所も何故だか自分でもわからないですけど・・・命がやっぱり一番重要だと思うようになったのかな。お金だけあっても、命なくなってしまったら駄目ですし。
【質問】先生のこれからのお仕事の上での目標を伺っていいですか?
仕事は無理はしないで、周りの地域の人たち来てくれる人たちの口の中の健康を見ていって、よく噛めるように。震災前はばりばりとやっていたんですけど、震災後は体が壊れちゃうと駄目だっていうのもあるし、ペースを落としてやっていけたらいいかなと思います。
|
|
あんてなしょっぷまちんど 千葉 ゆき 40代 女性
(平成27年3月17日大曲店にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
当日は矢本店で普通にお仕事してまして「あごら」(飲食店)の方はお昼もやっているので、休憩時間が2時から3時までなんですね。その1時間の休憩の時間に震災が来たんです。スタッフ3人で食事をとっていたらすごい揺れがきて,電気は消えるは、冷蔵庫は倒れるはで入口の柱に3人でつかまっていた状態でした。またすごい揺れがあって、社長が来て「大曲浜に6メートルの津波が来るから早く帰りなさい」ということで帰りました。
私は娘が二人小学校にいたので、赤井南小学校の方へ向かったんです。お姉ちゃんは(学校に)いたのですが、下の子は早く帰ってしまって(学校には)いませんでした。車で学校を出ようとしたら避難してくる車が多く出れず、走って家まで行きました。そしたらおじいさんの車に下の娘が乗っていたので一緒に南小まで戻りました。そこでやっと子どもと会えたのですがお姉ちゃんがジュースをこぼしてしまい(服が)濡れて寒いと言うのでもう1回家に戻ったんです。毛布を取っているうちに、隣の農協さんの方から黒い水が流れてきて「まずい」と思って、毛布を持って南小に向かったんですけど、もう小学校の廻りは水に浸かっていました。その時はあわてていて考えられなかったんでしょうね。有明の方から行けば行けるかなと思って、ぐるっと回ったんですけど、もちろんそこも前から水が迫ってくる感じだったんです。水に呑まれながらバックをして、道路が冠水して見えなかったので電柱にぶつかりそうになって止まった時に、右側に有明集会所に行く公園の前の道路がちょっと見えてたんです。そっちの方に行ったら、知っている保護者の方たちがいたので、「南小に行きたいんですけど」と言ったら「もう行けないよ」と言われ、そこ(有明集会所)で一夜を過ごすことになってしまいました。でも子どもたちは南小の体育館で、おじいさんはおばあさんを迎えに家に帰りもう南小に行けなくなったので家の2階で、その当日はみんなばらばらに過ごしたんですね。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
私たちも、震災の次の年の2月から8月まで銀座の方に毎月1回ずつ2泊3日で復興市みたいなイベントに行きました。そこでボランティアさん達に応援していただいて。今できることって何だろうみたいな感じで、私たちはアンテナショップなので、地元のPRの仕事だったので。とにかく今「復興に向けて東松島頑張ってますよ」ってことを関東の皆さんとかにPRできるよう毎月行くようになったんです。東松島だけでなく東北復興みたいな感じのイベントだったので、デパートの軒先でやらせてもらいました。
一般の方々にも励まされたのもたくさんありましたね。テレビで悲惨な情報が流れていたらしいですけど、「すごかったわよね」ってことで「頑張って」と言われることが多くて、それも励みになって毎月頑張って東京まで行ってたんです。そういう温かい言葉がすごく身にしみましたね。ボランティアさんも涙を流しながら「大変なのにそんなに元気で・・・」と言われたり、でもそうやって応援いただいている方々が一生懸命私たちのためにやってくれたからなので、本当にありがたかったですね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
アンテナショップは地元の人が、こんなに(地元に)いいものがあるってことをわかって他から来た人にPRでき「あそこに行けば何でもあるよ、わかるよ。」っていうような場所にしたいし、もちろん地元の人も集まってきてほしいです。それはアンテナショップを始める時から思っていることなんです。県内外全部みんな集まれる所になればいいかなと思ってます。今後も友好姉妹都市の物も置いてますし、派遣職員さんの所も帰ったとしても根強いファンの方もいらっしゃいますし、そこの繋がりもせっかくつないだ繋がりなので断つことはなく続けていきたいなとは思ってます。震災の時はいつもやってもらうばかりで、もう3年4年と経っていくにあたって自分たちでやらなきゃないという気持ちにみんな切り替わってきてるので、私たちも何か一緒になって自分たちでやっていかないと復興というものが見えてこないですよね。そこのところは頑張りたいなと思ってます。
|
|
 |
小野市民センタースタッフ
(平成24年7月11日 小野市民センターにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
高橋 広美 40代 女性
勤務中に被災
|
|
当日は所長と事務長と管理人さんと私の4人が勤務していました。揺れがおさまった時、防災無線で大津波警報が出ていたので、最初は片づけをしていたのですが、散らかった様子を記録し、写真を撮りました。小学校に子どもがいるし、牛網に実家の両親がいるので気になり、帰らせてもらいました。バッグに着替えとか非常食を持ち、親を迎えに行き、高台の小松台に避難しました。早かったので、道路は渋滞していませんでした。夕方5時位に戻ろうとしたのですが、アンダーパスが通行止めになっていて、戻れませんでした。家族6人で車の中で過ごそうとしたのですが、他に車に乗っている人たちも、婦人会の方が声をかけてくれ、分館の中に入れてくれました。その日の夜もおにぎりをいただき、次の日は外でさんまを炭火焼きしたりしてご馳走になりました。毛布も近所の方が貸してくれ、親切にしていただき、すごくありがたかったです。そこで2晩お世話になりました。
避難所には、一番多い時で260人いました。最後は市営住宅の方々の家が直るまで、8人が9月1日までいました。最初の何日間は夜中でも避難して来る人や、安否確認で人が来ていましたので、受付に交替でいました。交替で事務所に寝ていたのですが、なかなか寝られなかったです。最初は声がけして、水汲みやご飯作りの手伝いをお願いしていました。トイレが大変で、夜は真っ暗で見えないので、受付の所で懐中電灯で照らしたりお年寄りや怪我している人はおぶったりしていました。朝になると、凄い事になっていて、仮設のトイレが来るまで大変でした。避難者の方々に、わりと早い段階で部屋ごとに係を決めてもらって、動いてもらいました。電気は3月末には来ていたのですが、4月7日の地震でまた停電になりました。水が出たのは4月26日でしたが、3月中は給水車が来て、米軍のシャワーも来ていました。水が出るようになると、施設もきれいになりますね。
|
門馬 美樹子 30代 女性
仙台へ外出中に被災
|
|
(震災当日はセンターの仕事が)休みだったので、午後から友達と仙台港の夢メッセでイベントがあったので行っていました。凄い揺れで、私と友達とその子どもといたのですが、揺れがおさまるのを待っていたら周りは人がほとんどいなくなっていました。外に出て携帯でテレビを見たら、津波が6メートルとの予測が出ていたので、「ここはまずい」とすぐ車に乗って逃げようとしたのですが、信号が止まっていて、産業道路はすごく混んでいました。何とか45号線に出て塩釜に抜け、利府に出ました。そちらも、すごく混んでいて松島あたりも水が上がっていて通れないと言われたのですが、お互いの子どもが小野小学校にいるので、迎えに行かなくてはならないので、何とか帰りました。
私たちは、小野小学校の前の道が水が上がって通れなかったので、そのまま大塩市民センターに行きました。大塩も避難所になっていたので、友達は部屋の方に避難してもらい、私はお世話係のお手伝いをしました。夜中に牛網保育所から子ども11人と先生10人が避難してきました。婦人会の方が握ってくれたおにぎりを配ったりしました。夜は寒かったのですが、病気が心配だったので、窓を開けて換気をして回ったりしました。
次の日、水が引いたと思い、小野に戻ったのですが、郵便局のあたりは水があり、ざぶざぶと水の中を車で行きました。小野市民センターに行き、うちの旦那と子どもたちと数人は2階の視聴覚室に避難していました。大塩市民センターでお手伝いをしていたので、同じように受付を作り、避難者に住所と名前を書いてもらいました。お年寄りと怪我をしている人は和室で、それ以外の人は講堂にと分けていました。所長と事務長と管理人さんと市の職員が1~2人いました。私もここに勤務して、家族も避難していたので、ここが住居になっていました。高橋さんとは連絡が取れず、心配でログボートを出しウエットスーツを着て家まで探しに行きました。4日目に来て会えた時にはほっとしました。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
門馬 美樹子
|
|
今年は市民センター活動は増えましたね。趣味の教室は、仮設に支援の方が来ているので、ここで受講料を払ってまで参加する人はなかなかいなくて、開講できない状態ですね。生涯学習課のプラットホーム事業、みんなが元気になってくれる事業、いろいろ支援してくれる方の会場提供のみしたりしています。ここは拠り所なので、ものとかお金じゃなく、そういう形で支援、発信しています。避難所の時に避難していた人だけでなく、自宅にいた人も情報を聞きつけて参加してくれたりしています。家にいて片づけばかりしていると、頭がおかしくなる、ここに来れば楽しくなると来てくれます。市民センターが地域の人に近づいた感じで、近くに来れば顔を出してくれ、人がたくさん来てくれるようになりました。
|
|
|
辺見 園恵 女性
牛綱保育所(東松島市牛綱字上四十八27)で勤務中に被災
(平成24年7月27日 小野保育所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震が起きた時は子どもたちはお昼寝の時間だったのですが、子どもを集めて頭の上から布団をかけました。揺れが収まるのを待っていたんですけど、すごい揺れでした。所長の指示で、子どもたちをホールに集めました。津波がきたということで、所長が子どもたちを押入れに入れようと言いました。それで押入れに入れて、サッシなどを閉めることは閉めたんですけど、戸を閉めてもいたるところから水があがってきました。駄目だと思い、私はみんながいるホールのほうに向かいました。押入れがいっぱいだったので。他の先生はピアノに登っていて、早くと言われ、私も登ろうとピアノに手をかけた時には、腰まで水に漬かっていて、上がれと言われても、上がれませんでした。でも、たまたま水がきて、体が浮いたので、足をピアノにかけて、上に登りました。子どもたちは押入れの真ん中のところに上がったんですけど、水位が上がってきて、水に漬かるようになっていました。これでは駄目だから、押入れの天袋に入れようと、背の高い人が、季節の行事用の衣装ケースを出して、一番身軽な人がそこに登って、子どもたちを引き上げました。大人たちは押入れにあがったままで、天袋の柱につかまって水を凌いでいて、私たちはピアノの上に立った状態でした。
ピアノの上から外を見ると、雪がすごく降っていて、水がごうごうと流れていました。庭に停めてあった職員の車が、1台ずつ北側に向かって流れて、自分の車も流れていきました。子どもたちもギャーとかワーとか言うこともありませんでした。大人も子ども必死だったんです。なんというかいろんな偶然があって、通常、地震があったら、(避難所になっている)学習棟に行っていたんですが、行っていたら津波にのまれて危険な状態でした。たまたまお昼寝をしていて、布団が出ていたために、押入れが空いていたということと、天袋が高くて子どもたちを入れられたことも偶然でした。あのまま中段にいたら大人はなんとか押入れにしがみつけたと思いますが、子どもたちは押入れにつかまった状態でも、駄目だったかなと思います。
|
|
高橋 恵里子 60代 女性
東松島市内にて被災
(平成24年8月8日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震があった時は矢本の七十七銀行の中にいました。銀行の前に止めていた車に乗り込んだ時に車のラジオで3メートルの津波が来ます。とにかく避難して下さいって放送が流れていたんですね。でも、3メートルは凄いなと思っても、今まで経験していないから実際の津波の高さってわからない訳なんです。頭と気持ちと全部一致しない、地震が来た、津波が来る、3メートルって大きいんだろうけど、どの程度だろう?自分の身長から計算すればすぐわかることなんだけど、それが計算するまでいかないんですよ。実際は。
自宅のほんのちょっと手前でサラサラと水が来たんです。もしかしたら津波が来たのかなって、庭の向こう側を見たら遥か向こうの方に真っ黒な高い壁が見えたんです。このまま家に行っても駄目だろうし、このままもろに津波をかぶったら、たぶん流されて死ぬと思いました。自宅の2~3軒手前の家に門柱が建ってたんですね。私の体型よりは幅があるから、もし万が一津波が来てもそれが一度は津波の勢いを止めてくれるかもしれないと思って、そこの門柱にしがみついたとたんに、津波が来ちゃったんです。でも、ばさっと来たわけじゃなく、だんだん水位が上がってくる感じで、門柱にしがみついていたんだけど、津波の勢いが強くてしがみつくのが精一杯で、波の水位がどんどん上がっていくのと一緒に門柱をどんどん上って行ったんです。どうしようこれからと思ったその時、目の前を車が流れて行くんですよ。その次は船、その次は大きな樽。木や何かが当たるんですよね塀に、どんどんと音がして。
|
|
西村 結友 10代 女性
東松島市立鳴瀬第一中学校で被災。当時、中学2年生。
(平成24年11月11日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震が起きたときは、学校(鳴瀬一中)にいました。地震の次の日が本当は卒業式だったので、全校で準備をしていたんですよ。ちょうど準備が全部終わって、帰りの会をしているときに、地震が来て・・。たしか2日前にも地震があったので、そのときは普通に、「あぁ、また地震か」という軽い気持ちで。みんな、大丈夫でしょうという感じだったんですけど、やっぱり時間が経つごとに揺れが大きくなっていって・・。
校舎の3階に避難していたので、目の前が川だから全部見えるんですよ。水が上がったり、引いたりだとか。そのとき友達と一緒にいたんですけど、その様子を見ているだけで、涙が止まらなかったです。あふれそうになっているのに、車が動かなくなった人が川沿いに立っていたんですけど、見ているこっちはすごい危ないなというか・・。飲まれたらどうするんだろうって。
弟はそのときはまだ小学生で、小野小学校の6年生でした。(小野小に弟を)迎えに行ったんですけど、水が来てたので、今日は(帰すのは)無理ですって言われて。夜にようやく、じぃちゃんたちが七ヶ浜から戻って来て、中学校に迎えに来てくれたんです。(家には夜の)11時半くらいに帰れたんですけど、弟だけ小学校の方に泊まりました。ひとりだけで。わたしはじぃちゃんと戻りました。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
辛かったことより、嬉しかったことの方が自分の中ですごい大きいです。香川県の方に友達がいて、離れているので連絡がとれなかったんですけど、連絡がついたときにこっちのことを思って言葉をかけてくれたり・・。お互いそのときは中学生だったので、やっぱり募金するにも大きなお金ってできないじゃないですか。それなのに自分のお小遣いを募金してくれたりとか。あとはボランティア活動を通して支援してくれたりっていうのを聞いたので、自分たちだけの問題じゃなくて、同世代の子も頑張っているんだなってことを知ることができて、すごく嬉しかったなっていうのはありました。
|
|
鹿野 すづ子 50代 女性
自宅で被災
(平成25年6月13日 図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
震災当日は、だんなと畑仕事をしていました。午前中にジャガイモ植えを終えて、ゆっくり休んでいるところに地震がきました。すぐに堤防に上がったら、近所の人もみんな上がっていました。その時、川の水がこれまで見たこともないくらい引いていたんです。川底の木とかそういうものも見えました。今までの津波は10センチとか20センチなので、私たちもそんな感じで、避難なんてことは考えませんでした。
それから40分後くらいに堤防の下をパトカーが通ったんです。パトカーに「6メーター以上の津波がくるから逃げなさい」とお父さんは言われたようです。私たちは浜市小の校庭まで一旦行ったんですが、「校庭ではちょっと低いんではないかな」とお父さんが言い出し、矢本の滝山公園を目指そうということになりました。小野の畠山自動車(牛網字駅前)の方を通って滝山を目指したんですが、出たのが遅くて船橋電子(牛網字雉子抓)の後ろで津波にあいました。車から降りて立ったら、もものあたりまで水が来ていました。後ろを振り返ったら、2波目も来ていて、自衛隊(松島基地)の方からから浜市にかけて、一面真っ黒い山のような波が渦を巻いて迫ってきました。それを見た瞬間、自分は動けなくなってしまいました。腰がぬけたというか。お父さんには「早く歩け、歩け」と言われたんだけど動けなくて。お父さんには「動けない」って言えなくて「お父さん先に行ってて。後で行くから」とだけ言いました。お父さんは「何を言ってるんだ」と怒って、私を抱えながら国道沿いの熊野神社まで引きずり上げてくれました。その瞬間に2波目が大きく来て、車も流されました。かろうじて丘に一歩上がった瞬間に水が来たので助かったという感じでした。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
今後の教訓としては、地震を甘く見ないことですね。地震が来たら津波が来るというふうにとったほうがいいですね。前の私たちみたいに「10センチか20センチだべ(だろう)」なんて考えではなく、「また大きいのが来る」と思わないと助かりませんね。逃げ場所を自分たちなりに決めておくとか、普通の時にそういうことを確認しておくといいと思います。
我が家は集団移転を希望しないで、自分たちで何とかしたいと考えています。あえて津波が来たところを買いました。かさ上げして建てなければならないんですが、それでもやっぱり知っている人のそばがいいというか、この年で知らないところに行くのはいやですね。いつか家が建って、家から畑に出られる日がくるといいな、と思っています。子どもたちもとりあえず元気で仕事もあるので、私たちも子どもたちから元気をもらった感じです。子どもたちが働いているのに、自分たちが働かないでいられないよね、と。子どもたちは避難所から毎日毎日、普通に何も言わずに仕事に通っていました。それで私たちが救われたということですよね。
|
|
安倍 託子(あべ よりこ) 80代 女性
東松島市浜市
(平成25年6月20日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私いつでもね、避難訓練でも着るものとか、保険証とか全部たがえて(持って)行くのね。大きな袋に入れて。あとね、リュックに常に詰めて置くのね。長座布団2枚、どんぶく3枚、枕3個なじょして(どうやって)持って行ったかわかんないけど、とにかく持っていったんだね。隣近所さ(隣近所の人に)「浜市小学校にあばい(行こう)よ。」と声かけて。1人で歩いて3分の浜市小学校へ行ったんだね。
私は浜市小学校に逃げて行く時に、防災無線で「大津波警報」と3回言ったのは聞いたの。とにかく3階に上がって、長座布団2枚ひいて。近所の90歳以上のお婆さんたち、何人もいるのね。牛網、浜市みんな来たんだから、たいした人数なの。300人くらい来たって言ってたね。私はまだ津波が来なかったから、下に靴を脱いで置いてきたけど、私らが上がった後からは、校長先生が「そのまま上がれ」と土足であげたのね。私は、津波は見ないでしまった(見なかった)のね。場所取るのに、座布団に座って、そこで一晩過ごしたの。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
浜市にも港作った時の仕事歌あんのね。どや節って。「浜市どや節・甚句」って2つあんのね。防衛庁の防音対策で浜市はほとんど移転だっちゃ。そんで、「浜市さ残していきたい」って、私さ声掛ったのね。そんで6人で結成したの。今は、浜市小学校の生徒と父兄と運動会で踊り子してんの。どや節で。「えんやーどっと」って。あと後藤桃水まつりとか。
こないだね、大田区さ行って来たの。大ちゃん音頭歌ってきたの。今度、仮設対抗のど自慢あんの。それでも、歌ってけらいね(歌ってくださいね)、と言われて。お天道様出ない日あっても、おれの車が動かない日はないって言われるの。
今だにね、どこさ行ってもこの震災の話だよ。それこそ、どこの仮設に行ってもさ。私の住んでいる仮設でね、80歳5人してね、日、月、木を休みにして、夕方5時から6時までお茶飲み会やってんの。私は4畳半一つで、5人入られないから、前の家を借りて5人で集まってるの。最後に別れる時は「今日も1日御苦労さま。あはは」って3回笑って解散して来るの。
|
|
小田嶋 良枝 60代 女性
東松島市牛網字平岡
(平成26年3月18日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
強い地震が終わってもけっこう揺れてたんですよね。そして私、宮城県北部連続地震のこと思いだしたんですよ。あの時点で7年前ですね。「これでは駄目だ、停電にもなったし。うちでご飯も何も炊けないから」って思い国道出るとすぐコンビニあるんですよ。そこに水とかおにぎり、パンとか買いに行ったんです。コンビニも停電してたのでちょっと時間かかったんですよね。何とか買って、帰りに「一人暮らしの人がいる」と思って寄ったんですけど、もう誰もいなかったんです。近所見渡しても人気がないし、「あれ、みんな避難したんだろうか?私たちも避難しよう」って言っている時に、すごい音がしてきたんですよ。何て言うんだろう、コンクリートをがりがりって削るような音。「あれ、あの音なんだろう?」って言ったら、兄が外見たんでしょうね。「あっ、もう津波来ている!すぐ2階に上がれ」って言われて、玄関鍵閉めて私たちすぐ2階に上がったんですよ。
しばらくして妙に静かだなと思って、津波来たのは3時40分位だと言ってますよね。時間的によくわからないんですけど、平岡地区はたくさん家が建っているんですが立ち上がって見たら前の家は2階建てなのに、覗いたら妙に視野が広いんですよ。「あれ、何だろう?何かちょっと景色が違う」って「えっ、前のうちもうない!」って。それがもう流されてなかったんですよ。その前の家は平屋だったので、軒下まで水がだぶだぶってあったんですね。まだ明るいから4時半ごろでしょうかね。家は、階段の踊り場まで水が来てたのでどうしようもないんですよね。だから、下に降りて行くこともできないし、2階だけで3人でうろうろするほかなかったんですよね。隣近所の人の名前呼んでもどこの家も返事がないんですよ。日暮れてきたら、外も真っ暗で停電だから街灯も何もないでしょう。「私たちだけが避難しそびれたんだな」とその時思ったんですよね。とにかく水引かないから、下にも降りていけないし、2階に食べ物も何もなかったんですよね。寒いけど、2階には布団とかあったので、そこで一夜を過ごしたんですよね。寒いから身を寄せながらね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
浜市は行政区がなくなり、今元に戻っている人が10軒足らず7~8軒みたいなので、一つの町が津波でなくなっちゃたんですよね。それは、昔から住んでた町なのですごく残念だと思いますね。平岡地区も3分の2位移転しちゃったんです。流されたうちは1~2軒だったんですけど、浸水した家は壊して集団移転の所に行く人、自力で土地を求めて再建する人もいます。私の家ちょうど真ん中くらいなんですけど、そこから浜市側に向かって家が全部ないんです。あそこら辺みると、これから草とか生えてくると原野みたいなの。草ぼうぼう茂ってね。うちの裏側が海で、松林が海浜緑地公園から浜市までずっと続いてあんなに密集してた時は、海からうちまでがすごく遠いと思ってたのね。そしたら、松林がまばらで「こんなに海が近かったのかな」ってびっくりしたんです。1キロ以上1400メートルくらい離れてるみたいなんですよ。松林がいっぱいあって防風林、防災林になると思ってたので、まさかその松林が流されてもちろんうちにも入って来たんですよね。
いろんな所で津波の碑建ててますでしょ。牛網でもこの前除幕式あったの。小さい町でも、牛網と浜市混ぜて80人位犠牲になっているんですよね。それは、石碑とか建ててもらって後世に伝えてもらうことはいいことだなと思いました。
|
|
石森 康夫 50代 男性
石森 さと子 50代 女性
東松島市牛網字平岡
(平成26年3月23日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
石森 康夫
|
|
今まで全く経験のない位強かったし、長かったので「これは今まで考えられなかった事が起きるかもしれない」ってことで、小学校に逃げようということになりました。車で家族3人と、後ろのおばあさん(85歳くらい)を迎えに行って3人を小学校に置いてきて、またすぐ戻って。私消防団に入っているので浜市の消防団の人と二人で、浜市のポンプ積載車に乗って広報しながら、浜市の学習等施設とか鳴瀬川まで行きました。そしたら土手の上に何人かの人が上がっていて「見ろ、見ろ」って言うわけですよ。凄い勢いで川が上ってたんですね、逆流っていうか。「すぐ逃げろ」って言って、逃げてくる途中に浜市のおばあさんたち、知り合いではないんですけど、2~3人乗せて。玄関の戸を直してたり「こいつだけ(これだけ)片づけてから」とか言っているから「逃げないとまずいよ、すぐ乗れ」と二人ほど乗せて、道路歩いていた人も乗せて。そして浜市小学校に車入った時に、おばあさんたちよろよろ歩いていた人いて、もうそのおばあさん無理やり引きずって校舎の中に入ったとたん水がどかんときて、私は何とか濡れなくて助かりました。
|
|
石森 さと子
|
|
学校の先生が機転きかせて、停電になってすぐ車のワンセグで津波情報を知って、津波来る前に保健室から布団とか毛布、ブルーシートなど持っていったらしいですね。屋上の鍵も6年生の教室の近くに隠していたのを思い出して、下の階にあったから水没したら取れなかったんですけど、間一髪で屋上の鍵開けられたので上がれたんです。マニュアルとしては小学校の体育館が避難場所だったんです。1年前にもチリ津波の時も、校長先生が土足で3階に上げてくれたんです。「先生、掃除大変でしたね」と言ったら「この位はいいの。もちろん土足で上がってもらってよかったんです」とその時に聞いたので1年後の震災の時ももう迷わず、校長先生が玄関で出迎えてくれて「そのまま土足で上がって下さい」って言われて上がりました。
水が来た瞬間は、子どもさんもいたしちょっと泣き喚いた人もいたんです。「ここは、耐震補強しているから大丈夫だから安心して下さい」と私たちも言って先生方も言ってくれたし、怒って取り乱すような人もいなかったので、400人いたわりには整然と朝迎えられたような気がしますね。水もみんなで持っていった水を分けて飲んでいたし、不足すると大変なので、みんなが持ってきた水やお菓子を一括して集めて、それを少しずつ分けて「じゃあ、小学生に先にあげよう」とかおばあさんたちに食べていいよとかって、一晩だから過ごせたんですけどね、それが水引けなくて3日も4日だったらどうなってたかわからないんです。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
石森 康夫
|
|
私は農家なんで、農業用の倉庫も機械もすべて駄目になりました。しかし、うちの方は平成3年から任意の組合を作ってたんですね。震災の4~5年前に会社化したんですよ。それから田んぼも圃場整備っていう大きな田んぼにしていただいたんで、震災後1年だけ休みましたけどすぐほとんど復旧しました。今一部だけが復旧できてないんですけど、ほとんどの田んぼが復旧して施設も機械も国とか県、市のおかげで一通り揃えることができました。去年一昨年と2年間も米も作れるようになって今はいちごも始まりまして、とにかく仕事は年間ずっと通して何とかあるんですね。ただ問題は今からの後継者と、それからそこで働く人たちがきちんと仕事した分だけのお給料がいただけるようなしっかりした内容にしていかなければないなと、思っていることです。
津波かぶって、田んぼの土地力っていうのがまったくなくなってしまって、土のいい成分が全部掃いてしまったんですね。海から重金属とかいろんな悪いものも上がっているんで、田んぼの表面を全部掃いて捨ててしまったんです。また1から土造りをしてとにかく消費者に美味しいと言われる米を作って、きちんと数量も確保してそこで働く人たちの賃金がきちんと払えてってなれば、たぶん後継者も育つと思うんです。農業そのものに対して私もすごい誇りを持ってて、うちは何代も前から農家だけで食べてきたんで。とにかく頑張って頑張った分だけお金にも結果として必ず出てきますし。それはすごくいいことだと思うんで、ただ今、私の子どもたちはやらないと言ってるんで。うちの子どもたちじゃなくても誰でもいいんです、とにかく中には農家好きな人とか漁師好きな人とかいろんな人がいると思うんで。今はもう世襲みたいなのが必ずしもいいことではないし、だから農家やりたいという若い人が出てきたら地元でなくても、よそからの通いでもきちんとしていい仕事をして、後継者を育てるのが一番の目的だと思います。私は一応会社の取締役になっているんですけど、何しろみんな高齢化していて社長がもう66~67歳で私がまもなく56歳になるんですけど、いつまでも若くないんでとにかく20代30代のあとあとに受け継いでいけるような体制をきちんと取りたいなと思ってます。そのために、しっかりとした仕事をしてしっかりと稼いで利益をあげて、会社をきちんと良くして地元の皆さんからも信頼をいただいて「あそこだったらあの人だったら任せても大丈夫だね」と言われるようになりたいなと思います。
|
|
|
木村 茂信 60代 男性
(有)鳴瀬葬儀社・セレモニーホール花すみれ
(平成26年7月23日 (有)鳴瀬葬儀社にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
震災当日は、午前中宮戸の方の自宅葬だったお宅に、8日目で祭壇下げるために行ってたんです。宮戸ですから、午前中行って助かったんです。午後からだったら、帰ってくるのが3時半か4時ですから、津波に遭って帰って来れなかったか、途中浜で津波に遭って亡くなってたか、どちらかでしたね。(地震発生後)会館にマイクロバスあるので、こっち(自宅)に持って来て、今晩余震の時はバスの中で寝てもいいと思い、マイクロバスを取りに行ったんです。その時、何気なく川を見たら水が無くなっていて、潮が引いて下がっているのかなと思ってました。会館に行って、隣近所の人たちと「大変だったね」と話して、マイクロバスを運転して橋まで来たら、水が橋の高さいっぱいまで来ていたんです。最初、理解できなくて、「あれ!何だろう?」と思って。そしたら、家は流されて来る、人は流れて来る、「えっ?えっ!!」って感じで信号青になったら一気に(橋を)突っ走りました。娘たちも、小野駅前のサンクスに買い物に来てて、川で人が流されているのを見たらしいです。私自身も、川の水が引いている様子と、実際上がってくる様子を見ました。
災害の時には、ご遺体が体育館に集まっても、お棺とか中々入って来なかったです。だから、みんな仮埋葬という形になってしまったのです。1か月2か月経つと、体育館に置いておいても腐敗して見られた状態じゃないですからね。体育館の中は、臭いと体液ですごかったらしいです。着ていた物を、市では処理できないということで、仕方ないからお棺に入れたりして。それが、燃えなくていつまでも残るんですよね。それで釜が壊れるということで、この近辺どこでも火葬はしませんよと言われて。
仮埋葬の方たちを、土木関係の業者さんたちが掘り起こして、棺に入れ替えしてました。仮埋葬から半年後ですから、腐敗がものすごい状態でしたので、火葬場では釜に入れてから、住職のお勤めしてました。(亡くなった)みなさん、ヘドロで真っ黒くなって同じような顔してました。やっぱり恐怖と立ち向かって、波が来て「わぁ!!」と、ほとんどの人が目を開いたままでしたね。顔がチョコレート色になって、その人達を火葬して、骨がヘドロの色に染まってきれいに焼けなかったですね。これだけは、びっくりしましたね。昔、土葬で埋めて改葬って新しいお墓作った時、骨を掘り起こして火葬するんです。その時の状態で、土の色が骨まで染みついているんですが、ヘドロも同じ状態でした。
あるばあちゃんが言ってましたけど「葬儀屋さん、亡くなった人も可哀想だけど生きている人ももっと可哀想だ。俺が生きていて、高校生とかの孫がなんで死ななきゃないの。その負い目で夜も眠れない。これも本当に生き地獄だよ。なんで俺が助かって、嫁、孫が亡くなって、これほど地獄味わったことない。」生きている人も地獄、この言葉にはなんにも言うことできなかったですね。涙も感情も受け入れられないですね、そう言われて。これから死ぬまで、その人は一生地獄を見ていかなければならないなんて、こんな可哀想なことあるだろうかって。生きたために、逆に辛い思いをして。生きた人の地獄、亡くなった人たちの地獄。亡くなった人は、一瞬で済むけど、そのばあちゃんが亡くなるまで10年15年、それまで引きずらなきゃないのかなって。それが一番の課題でないですか。そこまで踏み込んだりできるのは、やっぱり葬儀屋だったかもしれないですね。そういう心の叫び聞けるっていうのは。
高校生の人が亡くなった時も、「よかった。戻ってきた」というのは、普通死んで戻ってきてよかったとは考えられないですよね。死んでご遺体あるのは当たり前の話ですから、ご遺体なくて葬儀やって成仏できるかなって言っているうちに、戻ってきて遺体を悲しむんじゃなくて、よかったっていうのは逆の言葉ですよね。一般の常識考えるとね。そういう言葉が拾えたというのは、末端に携わった私らかもしれませんね。
|
|
 |
武田 政夫 70代 男性
東松島市野蒜にて被災
(平成24年4月19日 ひびき工業団地 仮設住宅集会所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震が起きた時は東松島市野蒜の自宅でテレビを見ていました。大きな揺れがあり、これは大きな津波が来ると思った私は、家内と一緒に家から250メートル先の新町地区コミュニティセンターに避難しました。家内は犬も一緒に避難したいと言いましたが、今は犬どころではないと2人で逃げたのです。 コミュニティセンターには、すでに40人ほどの人が避難していました。センターの下には鳴瀬川が流れており、しばらくして津波が来ました。みるみるうちに水が増え、床から1メートルまで水に浸かってしまいました。
水が引いて少し落ち着いた時、最初に手を取り合って避難した家内がいないことに気がつきました。津波で私の家は流され、犬を連れに戻った家内は逃げることができなかったのだと思います。気づいていれば止めたのですが…。残念でなりません。家内は現在も見つかっていないのです。
5月14日からは仮設住宅に入ることができました。一人でも寂しいことはありません。仮設の人たちが「大丈夫ですか。どうしていますか」と毎日声をかけてくれるのです。安心して暮らすことができるのはうれしいことです。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
大震災後、忘れることができない出会いがありました。海外の若者が激励に来てくれたのです。昨年12月20日のことでした。通訳の日本人の女の人と一緒にエリザベスという女の子が私の仮設にやってきました。私は行方不明のままの家内の写真を仏壇に飾っています。それを見たエリザベスは、写真に向かって手を合わせてくれました。そのあと急にいなくなり、どうしたのだろうと思っていると20分くらいして花を買ってきて仏壇に飾ってくれたのです。それがうれしくて言葉も出ませんでした。その時、エリザベスを「日本人よりも日本人らしい女性だ」と思いました。彼女が通ってきたのは3日間でしたが、クリスマスイブの前日の夜には、自分でつくったという大きなケーキを3つ持ってきて、仮設の集会場でみんなを慰めてくれたのです。
最後の夜、部屋に呼んでお礼にカキと豆腐を入れた味噌汁とアサリ汁をつくってふるまうと、おいしいと言って食べてくれました。私は英語はできないのですが、単語を並べれば自然と通じるものです。別れる時には「おじいちゃん、とてもさびしい」と言ってくれました。その後、はがきが来て、今年6月頃にカナダに戻る時は日本に寄りたい、おじいちゃんをカナダに連れて行きたいと書いてありました。孫のようなエリザベスの気持ちがうれしくてなりません。いまでも文通は続いています。
エリザベスやロバート、明治大学の学生ら、見ず知らずの若者がなぜ私のところに来て激励してくれたのでしょうか。それは、一人でいる私を家内が元気でいるようにと後押しをしてくれているからなのかもしれません。きっと、そうだと思うのです。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
今は、あの津波のことはできるだけ思い出さないようにしようと思っていて、できるだけ楽しいことを考えるようにしています。ただ、一日中ひとりでいると、無性にさびしくなる時があります。「人は一人では生きていけない」と言うが、「一人でも生きていかなければならない」と思っています。食事のレパートリーが増えないので、栄養士さんに料理法を教えてもらったりしています。そんなことをしながら考えるのは、あの世に逝った奥さんがいろんな人とかかわりながら楽しく生きていくように後押ししてくれているのではないかということ。おおらかだった奥さんに倣って、明るく生きていきたいと思っています。
|
|
遠藤 惣之助 70代 男性
「えんまん亭」店主
東松島市野蒜の自宅にて被災
(平成24年6月1日 えんまん亭にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
震災当日は、地震の揺れがあって、まず私は外に出て様子を見ました。息子と二人で店の周りを見ると液状化が始まっていたため、これではだめだと車で避難することにしました。車で出ると、すでに亀岡橋で車が渋滞していました。家内が見たら、波が後ろの松の木を越えてきたというのです。その波が頭からでなく腹から当たったため、車はそのまま山側へ流されました。運よくエンジンがかかったままで、ハンドルを切ることができました。車の頭が沈まないように山側へハンドルを切りました。そこから車が流され始め、200メートルか300メートル流されたか、仙石線が脱線した野蒜駅付近まで行きました。
そこで、沈んでいた車か何かの上に乗り上げたようです。窓は開かない。水が入り込んで、その水を3、4回飲み込んでしまいました。ところが、その時後ろのガラスが割れていました。座席から背伸びをしたら、ちょうど割れたガラスから這い出ることができました。出たところにちょうど車が一台、続いてモーターボートが流れてきました。それを伝わり、二階建ての家に避難しました。巡回しているヘリコプターにそのライトを向けたところ、翌朝救助に来てくれました。自衛隊の霞の目に運ばれ、6日間お世話になりました。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
人間というのは寿命というか運というのか 同じ状況の中でも助かる人とそうでない人があるが、どんな状況にあっても負けてはだめだということだ。頑張れば希望はわいてくる。これからは若い人に頑張ってもらいたい。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
仮設にいると身体がなまります。何にもしないで食べて寝るの繰り返し。身体も動かさない。気持ちの支えもなくなれば自殺に至ることもあります。「店をやろう」と誘ってくれた息子の声におされ、店を再開することにしました。
店を再開してからはいろいろな人が来てくれました。仙台からわざわざ来てくれる方もあり、お客さんの顔を見ただけでうれしかったです。何時間も車を走らせてきたり、商工観光課に問い合わせたりという方もいました。
|
|
前谷 ヤイ子 50代 女性
自宅(東松島市東名)にて被災
(平成24年6月15日 グリーンタウン仮設住宅で取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は(家族)みんな一緒だったんですよ。息子たちは同級生や大親友も亡くなってショックだったみたいです。でも長男は4人を助けたんです。隣の家のほうから助けてという声が聞こえて、赤ちゃんをおんぶしている30歳くらいの親子と60代のご夫婦の4人が、流されていたんですね。息子が屋根から屋根へ、雪で滑りながら伝っていって、助けることができたみたいです。あとは自治会長の奥さんが、津波で私の家のところまで流れてきて、旦那が見たら、助けてとも言わずにずっと下にいたんです。旦那が飛び込んで助けたんですけど、そのあともずっと震えていて、いっぱい布団をかぶせてグルグル巻きにしたんです。家族で5人助けたんです。
その後自宅には4ヶ月いたんです。周りはみんな避難していましたから、うちだけだったんですよ。電気もないし水もこないけれど、家族4人で帰ってきたからしのがなくちゃいけないなと思いました。たまたま丸い石油ストーブを倉庫から出して2階に上げていて、給湯器には450リットル分水が入っていたんです。そこからちょろちょろと水が出てきているのを使って生き延びたんです。
車も流されてしまって、電話も繋がらない、とにかく情報がないので、流れてきたうちの自転車を直して、ヘドロの中を何時間もかけて市役所に行ったり、避難所を回ったり、市民センターに行ったりしました。だれが亡くなったとか、大変だなと、回りながら思いました。あのときは、とりあえず家の中のヘドロを片付けて、火をたいて、ちょろちょろ水を出して今日生きるのがやっとという生活をしていました。
私も気がおかしくなっていたんです。そんな時、東京のミュージカルの作曲の台本を書いている寺本さんのお家に1ヶ月間行ったんです。お風呂もあるし洗濯もできるからおいでと言われて。
被災した当時は、みんなバラバラだったんですけれど、支援も自衛隊や警察、電気関係、車のナンバーを見ても新潟、北海道など全国から来ていました。支援物資も頻繁ではなかったですけれど、私たちは(被災から)3週間後にもらいました。あとはみんなに聞いた体験談などを寺本さんにしゃべったんですよ。
うちの旦那は、水やカップラーメンをもらったとき、みんなが頭を下げるのをみて、もらうばっかりで胸が苦しくなるといっていました。私たちは何もできないけれど何度も支援してもらって、ありがとうと思っているということを寺本さんに言うと、それなら東京に行って、堂々と何もできない自分たちだけど、ありがとう、空元気でも良いから元気だよという気持ちを、ミュージカルでやってしまえばいいんじゃないのと言われました。寺本さんはミュージカルを40年も作り続けていて、私たちも肩身が狭かったし、みんな元気なかったし、何か前向きになれるキッカケになればと思いミュージカルをやることになって帰ってきました
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
うちの旦那は、水やカップラーメンをもらったとき、みんなが頭を下げるのをみて、もらうばっかりで胸が苦しくなるといっていました。私たちは何もできないけれど何度も支援してもらって、ありがとうと思っているということを寺本さんに言うと、それなら東京に行って、堂々と何もできない自分たちだけど、ありがとう、空元気でも良いから元気だよという気持ちを、ミュージカルでやってしまえばいいんじゃないのと言われました。寺本さんはミュージカルを40年も作り続けていて、私たちも肩身が狭かったし、みんな元気なかったし、何か前向きになれるキッカケになればと思いミュージカルをやることになって帰ってきました
東京からもいっぱい人が来たんですよ。素人の被災者がどんな練習をしているんだろう、その姿が良かったら協力しようということで、新聞社・雑誌社やテレビ局も取材に来て、撮っているカメラマンも泣いていたんですよ。東北大学や白百合女子大学の先生も号泣していて。毎回そんなことの繰り返しだったんですよ。あそこに身を寄せた人たちは何か手伝いたいと、支援してくれたんですよね。東京から色んなツテで集まっていただいて、私たちだけでは駄目で全国から支援があったので成功したんですよね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
ミュージカルをやったのは、元気にはなれなくても、いやなことを考える時間が減ればいいと、そうすればうつ状態も良くなると思ってのことだったんです。でも、私も体験したんですけど、歌いだすとみんな涙が出てくるんですよ。声が詰まって。みんな、自分の気持ちを我慢していたんですよ。避難所や色んなところに行く時には泣けなかったんです。だけど、歌いだすと体中の細胞がリフレッシュする、浄化されるというか。そうすると寺本さんに、「泣いていたら練習にならないだろうが。」と言われました。だんだん、みんなもお客さんにお金を払ってもらってやるんだから、と意識が変わって頑張って練習するようになりました。
ミュージカルだけじゃなく、みんなで集まって励ましあって一生懸命にやる、そういうことが生きる力になったのだと思います。震災後、こころのケアでカウンセリングを受けに精神科に行ったりすると思うんですけど、ミュージカルに参加した人たちはみんな直っちゃった。あとは次の段階に行くと思うんです。ミュージカルは終わってしまったけれど、その時にがんばれた、仲間ができたということが心の支えになっていると思います。
私は元々福島の人間なので、震災でみんな傷ついたけど、それに輪をかけてやっぱり放射能が大変なんですよ。実家のあたりも放射能が高くて、除染もなかなか進まないし、地元に帰れないんですよ。福島の子どもたちはみんなバラバラなんですよ。
そう考えると今回のミュージカルの経験を生かして、合唱でもいいんだけど、何かみんなが元気になれる、継続的に何かできるものをやりたいなと思うんです。特に、福島の場合は長期戦なので。そのために福島に行ってきたんですね。親のことや今後のことについて、情報を集めたいなと思い、東北大学の先生とかNPOなど、支援してくれる人たちとか色んな人たちの力を借りながら、お金をかけないで、福島の人たちが元気になれるようなものができないかと思っているんです。
これからは地域づくりで、市も市民協働課とか頑張っているとは思うんだけど、今回も私たちが動いたから援助してくれた。だから、私自身が動かないと。それと、頑張っているリーダーをみんなが支えることが必要なんです。リーダーとして頑張る人がけっこう自殺するんです。あんなに復興のために頑張っていたのにという人が。何かやろうというときに支えあえるような、そういう地域づくりが必要なのかなと思いました。
福島の人たちもそういうものを求めているわけですよ。被災して、みんなてんでバラバラで、故郷に戻れないからどこに戻ればいいかわからないので、私はその居場所作りをしたいんです。身近なところからやって、点と点をつないで線に、そして面にするように輪を広げていきたいと思っています。震災で大変な思いをした宮城の人も、人との輪をつくりながら、がんばるというか、1人で100歩はやめて、みんなで1歩、やれるところからやって欲しいなと思います。
子どもたちも、色んな経験をしたので震災を糧にして、世の中の役に立たなくちゃいけないんだ、という子がいっぱいいると思うので、それは楽しみな面もあります。
|
|
菊池 蘭 10代(小学4年生) 女性
野蒜自宅付近にて被災
(平成24年6月24日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は、塾に行く途中、お母さんと二人で車に乗っている時に、コメリ(牛網付近)の当りで地震にあいました。すぐに、野蒜小学校の近くの自宅に戻りました。気が動転していて、テレビや携帯の情報を聞くこともできなかったのですが、家の前にいた側溝工事の方が6メートルの津波が来ると教えてくれました。車に避難用袋を積んで避難する時に、飼っている猫と犬も連れて行きたかったのですが、お父さんに「ここまで来ないから、置いていけ」と言われ、猫は2階にかごに入れて置いてきました。
その時すでに小学校の前は渋滞していて行けず、歩いて小学校に向かおうとしている時に、後ろからバキバキバキとすごい音がしてきて、瓦礫の山が見たこともない高さで壁のように迫ってきました。近所の人たちが「逃げろー。山に上がれー。」と叫んでいたのですが、家の後ろの山なのですが、あまり上がったことがない山だったのでどこを登っていいかわからなく、でも何とか崖の上に登りました。今思えばとうてい登れないような山で、火事場の馬鹿力だったのですかね。その時は家の前を津波が来て、車が流されてました。
そこに、次の日の朝までずっといました。靴下も脱いでいて、ジャンパーも着てなかったのですごく寒かったのですが、非常用持ち出し袋のアルミ箔を着ていました。近所の人10数名で焚き火しながら過ごしました。夜は流された車のクラクションが鳴りっぱなしで、周りから「助けてー。助けてー。」という声が一晩中聞こえていましたが、どうすることもできず、今でも(思い出すから)夜がいやです。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
将来の自分の子供に、もし地震が来た時には、まず玄関に行って靴をはいて逃げる準備をしてと教えてあげたいです。10年~20年後の東松島市は災害のない町になってほしいです。
|
|
真籠 しのぶ 50代 女性
東松島市役所職員 保健師(平成24年3月退職)
野蒜駅付近にて被災
(平成24年6月28日 サポートセンターにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は、野蒜駅近くのお宅に訪問して帰る途中、松林の中で地震にあいました。ラジオで津波が来ると流れていたのですが、津波は東名運河を越えては来ないと聞き、市役所に帰ろうと思いました。でも、海側に行くのが怖く、いったん野蒜駅の2階の東松島公社に避難しました。野蒜小学校経由で帰ろうとしたらすごい渋滞で、結局、また野蒜駅に向かったのです。その途中で東名運河を逆流する津波が見えました。津波の時の対応の仕方、高台に逃げるっていうのがわからなかったので、目の前が山だったのにもかかわらず、車の中で津波を受けるしかなかったのです。
ヨットがぶつかって来たり、濁流にのまれて車の中に水が入ってきました。その時、ダウンジャケットは浮くという事も知らず、着衣水泳を思い出し上着を脱いでしまったんですね。車が上向きになり青空が見えた時、何かにぶつかりフロントガラスが割れてくれました。そこから脱出したのです。割れてくれたのは、運がよかったです。この世のものとは思えない光景で、まわりは全部海で、目の前は家が流され、人の気配はなく、生き残ったのは自分だけだと思ってしまいました。又津波が来て、真っ暗い水の中に沈み、右足はがれきにはさまったのか、もがいても上にいかず苦しくて、意識が遠のいた時にすごい楽なんだ、これが死ぬってことなんだと思いました。
でも、こんな所では死ねない、もう1回頑張ろうともがいたら足がはずれ、上に上がり何かにつかまりました。でも、怪我をしているし寒いから水が引くまで我慢できないと思い、水が少し引いた所を見計らって2階のある家まで行こうとしました。その時3人(おじいさん2人、おばあさん1人)が濡れながら、助けにきてくれました。2階まで上げてくれ、布団をかけてくれたけど、もの凄く寒かったです。
津波に対しての自分の知識の無さを本当に痛感ました。水は苦しくても、助かるためには飲まなきゃならないと思いました。ぐっと我慢なんてできないから、飲んで助かったと思います、逆に。検査結果も何ともなく、津波肺炎も大丈夫でした。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
私は運も良かったけど、家族のため、子どものために死ねないと、子どもからのメールだけを頼りに生きました。野蒜小学校付近で渋滞に巻き込まれた時、子どもからメールが来て心配させないように「お母さんは大丈夫」って返したんです。めったにメールをよこさない息子からも来て、すごく嬉しくて、あのメールがなかったら、生きて行けない。意識が遠のいて、死んだほうが楽なのですが、子どものために死ねないって強い思い、家族の愛って強いですね。運が良かっただけでなく、やっぱり家族だなと思いました。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
今までにない大災害だったので、保健師たちは役割を決めて、それぞれ分担してやりました。大変だったのは、薬が津波で流されてないので医療をスムーズに受けられなかったことです。病院に行くにもガソリンがない、車がないので、持病を持っている人たちを送って行くシステムも作りました。こちらから避難所とかに行き、慢性疾患を持っている人たちの悪化予防のために1日何十人か見たりしてみんなに感謝されました。あと、地元のお医者さんの協力で救護所を設置することもできたし、みんなの力がなければできなかったと思います。
今回良かったのは、日赤が開いていて相当機能していたことです。保健師たちが朝晩ミーティングに行っていました。日赤で、どこで何が足りないか、医療だけでなく、ミルク・オムツ・水など全部コーディネイトしてくれました。
避難所生活が長くなるにつれ、高齢者・障害を持っている方々が団体の中で暮らすことで、障害が悪化したり、高齢者が熱をだしたり、認知症がひどくなったりといったことが出てきて、そういう対応を避難所、保健センター、福祉避難所3カ所で連携してやりました。ここの町はそういう施設も被害を受けてなかったし、昼夜24時間体制で連携システムがきちんとしていたので、素晴らしかったです。それがあったからこそ悪化させないで、医療とか保健とかをやれたのかと思います。
|
|
渡部 順子 50代 女性
東名で野蒜生産組合の業務中に被災
山崎 清美 50代 女性
自宅にて被災
(平成24年7月5日 大塩市民センターにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
渡部 順子
|
|
あの日は東名の野蒜生産組合の事務をしていて、書類をコピーしたり準備してました。日本沈没じゃないけど駄目になりそうな揺れでした。でも、津波が来るなんて頭になく、津波警報も鳴りませんでした。大丈夫かなと思い、片づけとかしていたら、主人からの電話が繋がり「何やっているんだ。逃げろ。」と言われ、逃げたんです。
野蒜小学校の校庭の前で、渋滞で車が全然動かなくなりました。前の軽トラックの方が出たり入ったり周りの様子を見ていたようで、私の車のフロントガラスを叩いて「津波だ」とドアを開けて、手を引っ張ってくれました。体格のいい男の方だったので、引っ張られるままに行ったのですが、2~3歩くらい逃げた所で後からバアンと当たるものがあって、転んだら水だったのです。水の中でもがいて、赤い車が私に向かってくるのが見えてぶつかったら終わりかなと思っていたら、するっと車の下をくぐったのです。ずっと流されているうちは、真っ暗で何も見えないけどぐるんぐるん回っていて、水もだいぶ飲んでしまいました。これ以上水飲んだら私は終わりなのかなと、何分いたのかわからないけど長く感じました。
気が遠のいていくようになっていたら、小学校の教室の裏、山の方に流されて、ちょうど教室の側の所で浮きました。声も出せなく咳が出て、上から「大丈夫?」と声かけられました。消防用のホースにつかまれと言われたのですが、寒くて手が離れて落ちていまい、又浮いたのです。ロープを体に巻きつけろと言われたのですが、なかなかできず、何とか巻き付け、引っ張ってもらい、3階まで上げてもらいました。校舎の中に入れられ、カーテンを巻きつけてもらいました。でも、寒くて歯がガタガタでお礼が言いたくても言えない状態でした。何時間かしても、震えが止まらず、お母さん方に服を脱がせてもらい、子どもたちの体操着を着せてもらったのがありがたかったです。靴もないので、上靴入れを靴代わりにしてもらい、防空頭巾もかぶせてもらいました。そこでひと晩過ごしました。
|
|
山崎 清美
|
|
その日は家に私と母がいました。私は大津波警報を聞いていたので逃げようと言ったのですが、母がチリ津波もここまで来ないから「絶対逃げない。置いていけ」と強気になっていました。母一人置いていけないし、そうしたらかもめの大群が行ったから、絶対、津波が来ると思ったんです。松林側に耳をやったら、ゴーと音が聞こえ、遠くに波頭が見えました。「津波来たよ。2階に上がって」と私が上がり、母も付いて来て、2階に上がって窓を開け、ベランダに出ようと思ったら、ベランダが流されて行きました。周りが全部一瞬で海になったのです。遠くに波頭が見えて、上がったとたん物凄い速さで波が来ました。私は窓の桟につかまって、ジェットコースターのような速さで進み、隣の2階だけ残っているなと思ったとたん、そこで意識がなくなったんです。
意識が戻ったら、瓦礫に挟まっているようで頭がつぶされそうになっていて、つぶされて死ぬのかしら?苦しんで死ぬのかなって冷静に考えていました。川向うのコンビニまで600メートル位流されて、その脇に大きな船が流されていました。瓦礫の間に母が挟まれて、苦しい苦しいと騒いでいて、叔父と二人で瓦礫を動かそうとしたのですが、全然動かなかったです。「助けて。助けて」と騒いでいたら、若い夫婦が来てくれ、のこぎりを持って来てくれて、助けてくれたのです。その人たちが毛布や布団、ホッカイロを持ってきてくれました。
夜になり、水が引いていたのですが、ヘリコプターが飛んでいたので、携帯の灯りで「助けて」とやったのですが、見えなかったようです。外の瓦礫の上にいて、瓦礫が動くし近くの家のガスボンベがシューシューいっていて怖かったので、すごい高さの瓦礫から降りました。雪が降ってきて、毛布や布団は濡れるし寒かったのですが、バックが濡れてなかったので、ヤクルトを飲みました。小学校に避難したかったのですが、夜中で危なかったので朝まで待ちました。星があんなにきれいな空を初めて見ました。
明るくなってきたのでヘドロの中、靴もない状態で、3人で難民状態で歩いて行く途中、周りは家が倒れて流され、信じられない、現実じゃない夢だよねと思いました。野蒜小学校まで行って、上に行ったら「大変だったでしょう」と服を脱がせてくれ、体操服を着せてくれ、こすって、温めてくれました。母は低体温になっていると、ヘリで日赤に運ばれましたが、何ともなく無事で、その後は中津山小学校に避難しました。私は自衛隊の人におんぶされ、下まで行き小野市民センターに行きました。看護学校の生徒がいてお世話をしてくれてました。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
渡部 順子
|
|
今家族の大事さがよくわかりました。家族が一番心配してくれ、支えられて、みんなに感謝する気持ちが出てきました。生かされていると思います。
|
山崎 清美
|
|
いつ何が起きるかわからないので、世間に迷惑をかけなければ、自分の生きたいように生きたいと思います。いろんなことを我慢しながら、何かいろいろしたい、死にたくない死にたくないと思いながら、亡くなっていった人がたくさんいるので、誰に何を思われてもいいという感じに変わりました。家族も震災後の方がまとまったと思います。家族がみんな助かって、揃っているのは当たり前のことなんだけど、幸せなことなんだとしみじみ思います。
|
|
|
野蒜保育所
勤務中に被災
(平成24年7月14日 小野保育所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
後藤 誓子 野蒜保育所 所長
|
|
2時46分、いつもより激しい揺れを感じ、まず各部屋を回りました。一番最初にお昼寝中の2才児クラスの部屋を回って様子を確認。事務室に戻り、揺れが治まるのを待ちました。まもなく防災無線から「大津波警報」と聞こえました。「逃げなきゃ」という思いで、各部屋に「逃げるよー」とお触れを出しました。
運河を越えれば野蒜小学校だから、そこまでは二十数分なので頑張ってとにかく歩かなきゃということで歩き始めました。あるおじいさんが「車に乗せてけっからー」って言ってくれたんです。「じゃあみんな乗せてもらっていいよー」ていうことで乗せてもらいました。あとで調べたらそのおじいちゃんの車を含め6台に分乗しました。途中、ちょっと渋滞のところが何箇所かあって、太田屋さん(野蒜字北赤崎)の角を曲がったら、車がもう動かなかったんです。何とか先生方も誘導してもらったおかげで校庭に入ることができたし、体育館に一番近いところに止めることもできました。そこから子どもを運ぶのも、その辺りにお家の方がいたので、運ぶのを手伝ってもらうことができました。
その時、子どもは78人中、早退・欠席者を除いて70人いました。地震後に保護者がお迎え来て、野蒜小に運んだのは35人でした。あとで確認したら、残っていた子は12人でした。35人のうちの12人でした。お迎えがきたもののその場で帰らず、家族で避難していた子が17人でした。あわせて29人もいました。
3時30分には着いていたという感じですね。そして、「津波だー」という声と「水だー」という声が聞こえました。「舞台に上がってー」「ステージに上がってー」という声も聞こえました。私も膝が悪いんだけど、誰にも助けてもらわないでステージに一人で上がったんだよね。後から行ってみたらずいぶん高いんですよね。
わたしは、舞台の上で斜めになった演台につかまりました。「どこに流れるんだろう」というところから記憶が始まっているので、その間、どうやってつかまっていたかもわからないんです。子どもを入れて5人でただ流されていたんです。たまたま運よく、上から見ると渦巻いていたようで、ギャラリーに流れ着いたんです。そして上から助けられました。
水が引いてから、みんなギャラリーに上がったんですけど、一人の先生が「子どもを放した」と半分泣きながら来たんです。私も何とも声をかけられずに、どうなったかなあ、と思っていました。水の下が見えるようになってから反対側のギャラリーを探しに行きました。人もぎっちりだったんですけど、子どもの確認をしなければならなかったので、ぐるりと回って反対側のとこまでずっと見ながらいったんです。
放した子どもをどう助けたかというと、用務員さんが舞台からフロアに投げ出されて、水があるから立ち泳ぎしていたら、子どもだがなんだがザッブーンって流れてきたらしいです。ダウンのジャンパーを着ていたんです。その子。だから身体がプックーって浮いたんです。誰だと思って返してみたら、見たことがある子だって。どうしたらいいんだろうと考えていたら、畳が流れてきたから、そこに子どもをぽんと乗せて、自分が乗ったら沈んでしまうので、自分は立ち泳ぎをしてその畳を舞台のほうまで運んできて、とにかく舞台にいる人に「お願いします」って言ったところを後藤先生が見ていたんだよね。
一人一人名前を呼んで、「○○ちゃんいます」「○○ちゃんいます」って言うんで「あー、残った人は全部いたなあ」って思ったのよ。まだ確認しない時は、どの子どもの名前を呼んでも、先生の名前を呼んでも誰も返事しなくて。もう先生たちも、子どもたちも亡くなったんでないかと思って、もう気違いみたいにして名前を呼んで。
体育館に津波が入ってきたのは3時52分。つかまって何分で流れ着いたか時間の感覚がわからない。水が引いたときは真っ暗ではなかった。3時52分は時間的に暗い時間ではなかったけれど、津波が来るせいか、いつもよりどんよりしていました。雪が降っていたから?
子どもが12人残っていて、先生方も私らがみんな助けたわけでなく、住民の人に助けてもらったから、ねえ。誰が亡くなってもおかしくない状況だったもんでね。
寒さでだか溺れてだか、とにかく二人の子が泡を吹いてしまって。それでも先生方が一生懸命背中をさすってくれていて、「どうにかもどりました」って言われた時に「じゃあ、こっちのほうはお願いね」って先生方に頼んで、わたしはまた戻って、10時半か11時くらいの間かな、たぶん学校に行く道路を住民の人たちがどうにか歩けるようにしてくれたのか、がれきの中を歩きました。体育館から校舎3階に移りました。途中、がれきのあったところは、ご父兄が自分のひざに乗せてくれたんですよ。わたしも乗せてもらいました。だから次の日そこが真っ黒。踏み台がないと上れない状況だったので何百人も乗せてくれたはずです。
野蒜小学校3階に上がってからは一晩寒くて。子どもたちは運動着が置いてあって。おにいちゃんたちの。住民の人たちは私たちが行く前に着替えさせてくれていました。移動するのも助けてもらって、おばあちゃんたちが手伝ってくれました。わたしたちは凍りそうだったね。朝まで固まって、みんなで寄り添っていました。ほんの少し寝たのかな。交代で抱っこしたり。
子どもたちもああいうときは泣かないですね。不思議と泣かないし、困らせないし。かわいそうなくらい。次の日の夕方までほとんどの親が引き取りに来ました。その後、鳴瀬一中に移動したのが15日の午後でした。
市内で千何人亡くなっているうち、野蒜で500人亡くなっているんですよね。運よく生き延びたとしか思えないよね。
子どもたちの様子は、元気でいるかのように見えます。この一年間、夢中になって生活してきているのは大人も子どもも同じです。一年過ぎて、いろんな思いが出てきているようです。お兄ちゃんを亡くした子が、今まで何も言わなかったのに、今頃になっておかあさんに、「ぼく死んでおにいちゃんのところへ行きたいな」なんて言うらしいです。まだお兄ちゃんの死が受け入れられないのか、「お兄ちゃんのお誕生会したんだよ」なんて話したりしています。まだ受け入れられないけど、受け入れなければならないとは思っているようです。
今年度の児童は79人です。野蒜と牛網と小野の三つの保育所が集まって、4月14日からここじゃなくて、地区センターで始めたんですけど、その時は野蒜保育所の子どもは40人くらいしか集まらなかったんですね。仙台に行ったり、あちこち散らばったりしていました。
震災後は、津波ごっこなどがありました。でも、8月くらいにはなくなりました。積み木を見れば、「つなみだー」って言って倒してみたり。自分が経験しなくても、テレビでずっと映像が流れていたしね。津波を経験してひっくり返ってた子は、5月の連休までお風呂には入れなかったということです。
|
|
後藤 悦子 野蒜保育所 保育士
|
|
そのときの体育館には小学校の子どもたちもいたし、おじいさんおばあさんたちもいたし、不老園の人たちもちょうどぞろぞろ入ってきたところでした。私は毛布を持ってきてくれたお父さんがうちのクラスのお父さんで、毛布に入りながらおしゃべりしてたんです。「来たー」って聞こえて、でも何がきたのかわからなくて。みんなが一斉にステージに走り出して、私もつられて走りました。その子をステージに上げて、他にも足元にいた子を何人か上げたかと思うんです。投げ入れたというか。それから自分もステージに上がりました。そうしたら偶然所長先生の背中が見えたんです。「所長先生」って呼んだら所長先生が振り返ったので、誰かわからないけどそこにいた誰かを「お願い」って投げたんです。
わたしはステージに上がって、最初にクラスの子を抱っこし、それから隣のクラスの当時2才の子を抱っこしました。でも、行くところがないので、ステージの壁のところまで追い詰められる感じでした。水がバーっときて、カーテンというか暗幕にしがみついて、片手でクラスの子を抱っこして、もう一人の2才の女の子には先生に捕まってなさいよと言ったらしっかりしがみついて「えー」っと声をあげたけど、泣かなかったです。水がバーっときて首まで浸かったら、わたしもフリースの厚いジャンパーを着てたので、すごく重くてどうしても片手では沈んでしまうんです。しょうがないので子どもを放しました。子どもがぶくぶく沈んでいくのをサッカーのリフティングのようにひざでボンと蹴り上げて、また沈んでいくのを蹴り上げと、何度も何度も繰り返しました。男の子も何度も沈んで水を飲んでパニック状態になり、ギャーギャー泣き叫んでいましたが、どうすることもできませんでした。男の子を抱き上げれば三人とも沈んでしまうし。後から考えれば着衣泳などもあったのに全然わからなかったし、かわいそうなことをしたなあと思います。
国井先生は、水が引いたら「子どもの手を放した 放した」ってパニックになっていて。でも、何気なく見たら畳にちょこんと乗って舞台の上に流れ着いていて、「あそこにいるよ」ってなって、私が上から流れ着いたところに迎えに行ったんです。誰かが受け止めてくれてそこにおいてくれたものなのか、たまたまそこに流れ着いたものなのか、そこにちょこんと座っていたんですね。ぼーっとして。
水が引いたとき、誰かが、時計側のほうにギャラリーに上がる階段があるっていう話になって。そうしたら、放送室側の壁にだれかが穴を開けてくれたんですよ。そんなに大きい穴じゃなかったけど。そしたらそこに誰かが、ステージにあった階段を立てかけて、まず子どもからっていうことで、私が下で上げる人、もう一人2歳児の担任が真ん中にいて、あるお母さんが上から引っ張る人になり、次々と子どもをギャラリーに上げました。他の先生やもう一人の2歳児の先生はステージから保育所の子がいないかどうかを確認し、連れてきて、次々上げるようにしました。畳の上にいた子どもは私が抱っこして、最初にあげてやりました。
夜になって校舎に移る時に「今、道を作っているから」っていうことで待っていました。一斉に行くとパニックになるので、20人くらいずつのグループで、しかも子どもから移動しましょうということになりました。私は母と一緒で、子どもたちがいた放送室と反対側のギャラリーだったので、子どもたちがぞろぞろ行くのが見えたんです。
車が重なったところを上行ったり、下くぐったり。やっと校舎の入り口まで行ったら、3階までの階段の遠いこと遠いこと。重い母を抱えて、3階までの階段が長くて長くて。そしたら途中で、ご父兄が「あら、先生だっちゃ」って言って、母を抱えてくれて、途中から上げてくれて、ほんとに助かりました。
家は野蒜保育所のすぐ近くなので、すっかりなくなってしまいました。夜が明けた時の、音楽室の窓から見た景色はびっくりでしたね。下を見ると、消防の人が板みたいなのに遺体を乗せて体育館に運んでいて、次の日には自衛隊さんが遺体を収容していました。
津波の高さが10mって言われても、具体的にどれくらいだかわからないですよね。母と一緒に逃げてきたおばちゃんは、それこそお菓子とかみかんとか持って(笑)、そういう感覚だったんです。
|
|
国井 春美 野蒜保育所 保育士
|
|
急いでみんながステージに上がる足音も聞こえました。わたしもステージに上がったときは一人でしたが、あっという間に水が首まで来て、ちょうど子どもが2人いて、最初は2人抱っこしたけど、やっぱり水圧で抱っこできなくて一人放してしまいました。一人は抱っこできたんで後は立ち泳ぎしていたのか、よくわからないんです。しかも暗幕につかまって落ちないようにしていました。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
後藤 誓子
|
|
避難状況を書いたものがあるんです。東松山市から依頼を受けて二回ほどお話をしてきました。支援を受けたところは、取材にも応じました。後の人たちに残していかなければという思いからです。
|
|
|
制野 俊弘 40代 男性
東松島市立鳴瀬第二中学校 教諭
野蒜「かんぽの宿」で被災
(平成24年7月26日 鳴瀬第二中学校仮設校舎にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
大震災の当日、午前中に鳴瀬二中の卒業式が終わりまして、午後2時頃、かんぽの宿に行きまして、その時には祝う会が始まっていたんですが、80名くらいの規模で1階でやってました。そこで地震が来て、一旦、子どもたちを低いテーブルの下に入れて、一時避難というような形だったんですけれども、揺れが収まった段階で、かんぽの宿の支配人から大津波警報が出ていますということで、この建物は大丈夫なのですぐに上の方に避難してくださいということでした。その時点では、確か6メートルぐらいという話だったと思うんですが、すぐに10メートルという話が出て、10メートルではまずいということで、4階に、生徒、保護者、宿泊者が総勢200人ぐらい避難しました。
それでも高さ10メートルでは危ないのでないかということで、屋上に逃げたんです。それが大体3時ごろだったと思うんですが、車椅子の人、ご老人の方を最初に上げて、中学生は一番最後ということで全員屋上に上がったんです。上がって30分ぐらい吹雪の中で耐えていたんですが、丹前とか皆さんある物をかぶっていたんですが、寒さに耐えられなくなって、冷えてきたので、もう一回4階に下がったんです。その後10分ぐらいたって、子どもたちが津波来たというので海の方を見たら、松の木の間から最初ちょろちょろ波が入って来たと思っていたら、一気にどかんという感じで波が入ってきて、目の前が松林なんですが、松林が全部なぎ倒されるような光景でした。下の方には車があったんですが、それも全部流されるような形で、一気に水かさが上がりました。
その時、子どもたちは結構パニック状態、親たちもパニック状態でした。女の子2人が過呼吸になったので別室に連れていって、お母さんたちが介抱してました。私たちは子どもたちに大丈夫だからと言って落ち着かせていました。津波が入ってくる瞬間から見ていたので、どこまで上がるのか恐怖でした。支配人からは、4階で6から7メートルくらいしかないと言われていたので、10メートルと聞いて、みんな青くなっていたんです、実は。結局2階ぐらいまで津波が来て、4階までは幸い、来ませんでした。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
震災を経験して子どもたちが強くなった部分は、目には見えないんですけど、親たちの大変さは、今、しっかり見ている状況だと思うんですね。中には職失った人もいるだろうし、新しい職業に就いたりとか、慣れない土地で生活とか、狭い家とか、とにかく親たちの頑張りを見てるということは、今までよりは、中学生をちょっと大人にしてるのかなというところはありますよね。勉強を頑張り出した子どももいるし、去年は駅伝をうんと頑張ったり、野球頑張ったりとかしてたので、大人になったのかなというところはありますね。ましたよ。
|
|
安海 武英 40代 男性
東松島市立野蒜小学校 教諭
職場(野蒜小学校)にて被災
(平成24年8月1日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震の時、代表委員会を開催していたんです。どーんと、揺れが物すごく強かったので3年生の子どもが泣いてしまったんですが、子どもたちは普段避難訓練やっているので、我々が言う前に、すぐ机の下に潜っていました。代表委員会を開いていた教室の天井からつるされたテレビが、すごく揺れていたので、それが落ちてこないか心配でした。揺れがなかなか収まらなかったので、とにかく、子どもたちには、先生が指示を出すまでそこから出ないようにと話しました。揺れが収まってから、体育館に避難するとなって行きました。
そうこうしているうちに、津波が来ているという情報がたくさん出てくるようになって、校長先生は校舎の方に避難させると判断され、体育館にいる人たちを校舎に避難誘導するようにと、私に指示がありました。大きい声出して「皆さん今から校舎に避難しますので私に付いて来て下さい。」と言って、私が先頭になって体育館の出入り口に向かおうとしたときに、外で車がぷかぷかと浮いているのが見えたんです。さらには波が黒い固まりになって押し寄せるのが見えたので、ああだめだ(校舎に行けない)となって、「早く逃げて、体育館の上に上がって」と指示しました。みんな「わー」となって、体育館の中に散らばったんです。ギャラリーに上がって行く人もあれば、ギャラリーの近くでない人はステージに上がっていました。
夕方、校庭見たら、すごい瓦れきの山になっているので、これでは動けないと、校舎に教頭先生残っていたんですけど情報をやりとりしたら、連絡を入れてもつながらないので、まずはその場所で待機するとなりました。段々日が暮れて、暗くなってきて、寒いし、当時の校長先生がみんなに声かけてくれて、それに救われている人も多分たくさんいたのではないかと思います。6年生の女の子がファイトとかいう声かけたりして、こういう逆境の中で声出せるなんてすごいなと思いました。私なんかへとへとでそんな声なんて出せなかったですね。みんなで声かけあってお互い励まし合っていましたね。
夜中に地区の消防団の人が来て、足場確保するのでもうちょっとお待ち下さいという声が聞こえた時に、ああここからようやく出れるんだなと思いました。それから30分くらいしてから道を確保できたので、小さい子どもさんとかお年寄りとか体調悪い人から順番に移動を開始しました。
校舎もすごいことになっていて、いろんな物が入っていて、真っ黒になっていました。中に避難していた人がアルコールランプをともして明るくしてくれましたね。学校の裏まで津波が来てますので、車で浮かんでいた人を消火栓のホースを出して、それをロープ代わりにして救出したようです。あるおじいさんは、指を切断してかなり血を出していたとのことでしたね。
2階の特別支援学級の教室を野蒜小学校の職員の部屋として使って対応することにして、私たちはそこに集まったんです。その隣の理科室が本部となって市役所、消防の人たちが対応しました。その時点では、子どもたちは70人ぐらいいたと思います。親御さんが迎えに来た人もいたし、避難している親御さんとそのまま学校にいた子どももいました。私が家に帰れたのは3日目でした。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
校舎に移動して、わりとすぐ、中下(なかしも)地区の人たちから差し入れが来たんです、おにぎりとかですね、それは本当にうれしかったですね。当然数足りないんですけど、子どもたちに渡せました。それから、少したってから市から救援物資として食パンとジャムが届きまして、ありがたかったですね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
震災を経験して後世に伝えたいことは、負けない気持ち、強い体と、強い心を持っていないと駄目なんだなと思います。それがないと前に進めないし、人も助けられないと思います。もちろん、それがないと自分を守れないので。前向きな気持ちが、不便なところもプラスに変えていけると思いますね。
|
|
内海 牧子 60代 女性
主任児童委員
石巻蛇田イオンショッピングセンターで被災
(平成24年8月11日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
震災発生時は蛇田イオンにいました。2分ほどで天井が落ちちゃったんだけど、落ちる寸前、波打ってましたね。しばらくして落ち着いたら、「みんなで蛇田中学校の3階に避難しますよ」って、店員さんが全員でお客さんを引き連れて脱出したのですが、私はそれどころじゃなくて、「野蒜に帰らなくちゃ」って。自分の車に乗って、野蒜に向かったんです。三陸道か農道か迷ったんだけど、農道を通ってきて、いつも20分くらいでくるところを、1時間くらいかかったんですね。ようやく西保育所や願成寺のところまできたら、もうそこで通行止め。45号線は波があがってきているし、願成寺から西保育所にちょっと行ったところの信号の前もがけ崩れになっていて、瓦礫は山ほどあった。そこでも係りがいて通行止めで、野蒜に戻れないよってことだったんで、願成寺に戻ったの。
願成寺の下も水がきていたんですよ。あとは車の中でラジオをつけたりしてました。どんどん雪が降ってくるし。それが3時くらい。2時45分頃の地震で願成寺に戻ってきたのは4時近く。その時もう津波がきてたのね。ラジオで「津波がドンドン押し寄せて、野蒜方面の家が流されています」「野蒜小学校の2階まで水があがってきました」って放送がありました。もうこれは何だろう、信じられないと思ったね。
朝の5時か6時頃。その頃には波が引けたから、とにかく野蒜に向かいました。周りは山のくらい瓦礫があったけど、45号線だけは行き来できるように、どかしたんですよね。どんどん野蒜のほうに行ったら、中下あたりはなんともないのね。「ああなんともないんだ」と思いながら、どんどん野蒜小学校に向かって、亀岡ってあるんだけど、あそこまで来たら、もうすっかり渋滞。みんな車で逃げてきたんだね。野蒜小のほうを見たら、これはどうした、もう信じられない、という光景でした。家は流され、車は流され、小学校の前に山積みになっていたの。そのほかに電柱やら建物が全部なぎ倒され、道路も何もないわけね。それこそ戦争でないけど、地獄の世界。見た瞬間、震えがきてね。
|
|
櫻井 りつ子 50代 女性
東松島市大塚
野蒜「かんぽの宿」にて被災
(平成24年9月4日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
当日は中学生の娘の卒業式で、懇親会がもうそろそろお開きという時に地震が来ました。
(会場だった「かんぽの宿」の)2階、3階、4階、屋上と登っていきました。屋上は寒くて無理だということで最終的には4階で一晩過ごしましたね。一晩長かったぁ、揺れてね、クラクションも鳴っているしね。私達の命が助かったのは寒いところじゃなかったから、何もなかったけど布団があったおかげで、寒さをしのげたのが本当によかった。
朝、出発して、まず小学校に行ったんですがすごい状態で、「こりゃあダメだー」と・・。次に定林寺さんの方に行ったんですが、そこも身動きがとれない状態で。中下にも避難できる場所があるって言うんで歩いて行ったんですが、そこもいっぱいでした。「あー、自分たち入ったらもっときつくなるのかなぁ」ってね・・。
3人と1匹で、すごい格好で歩きました。浴衣を着て、バスタオルをかぶったり、毛布をかぶったりしてね。どろどろの格好ですよ、靴もズボンも。「どこもいっぱいでどうしよう・・」って。じゃあ、大塚まで行ってみようということで引き返しました。裏道を通って行こうとしたときに、同級生のお母さんに「りつ子さーん」って声かけられたんです。「いやぁ、今どこもいっぱいで・・」って言ったら「うちに来なさい」って。「こんな格好だからぁ」って言ったんだけど、「いいからぁ」って言われて。中下にある家ですね。上から下まで全部着せてもらいました。水道もだめで水もないから雪を集めて、その雪で泥を落として家に入りましたね。あったかい布団を用意してくれてね・・。あのときは冷凍庫もぜんぶ電気が切れてるから、大きい鮭を焼いて、鮭とおにぎりをいただきました。本当に良くしてもらってね。「そう言えば昨日、誕生日だったよね」って。3月11日が誕生日だったんですよ。そうしたら「うちの人も3月11日でさぁ、ケーキ買っておいたんだけれども・・」って。ぐちゃーっとつぶれたケーキだったんだけど「今日みんなで(お祝いを)しよう」って言ってそのケーキをみんなでご馳走になったんですよ。そこには、ぴいちゃんと、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、息子2が人いて、あとワンちゃんが2匹いました。それなのに自分たちにも分けてくれたんですよね・・。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
コタツの台が被災しないで物置にあったんですね。その台を裏玄関に置いて、そこにボランティアさんたちに向けてメッセージを書いたんですよ。言葉では伝えたんですが、その後は会わないじゃないですか。ボードにありがとうございますって書いたら、ボランティアさんたちも「あのときは冷たいタオルありがとうございます」とか「また来ます」とか書いてくれてね。後から奥さんを連れて来た方もいましたね。「ここ、自分たちが(きれいに)したんだよ、ここはすごく印象に残っているんだ」って。なにしろ元気よく掃除していたもんでね。だから、そう言ってもらえたのかなぁ。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
自分は何かしてないと不安だったんですよね・・いまは家のことで頭がいっぱいですけど、家が落ち着いたら今度は何を考えんのかなぁって。将来は高台移転かなぁ、まず家に落ち着いて、次にまた考えようかなって思っています。立派なことはできないので、本当に自分のためなんですよ。でもこうして見ると、自分が幸せな平和な気持ちでいれれば、人に優しくなれたりするのかなって思いますね。自分が不安だったりしたら、人のことが見えないもんね。自分のことしかね・・。だから少しでも、自分がいい心でいるには何をしたらいいかなって思って、やっぱり前に進んで、何か困っている人がいたらお助けできたらいいかなぁって。まずは自分がね、平和にしていないと人の幸せにも手助けできないのかなぁって思いますね。まず、家庭を第一にして。そういうのを今回感じましたね、いままでがあたりまえすぎてね。幸せすぎたんですね、きっと。気づかないでいたんですね。家族でいっぱい喧嘩するんですけどね、泣きながら喧嘩して・・ただ、被災後のことというか、東名の家のことはやっぱり口に出さないですね。あまり言わないように・・たぶん言うとみんな(涙が)ポロッとなるから言わないのかなぁ。でも、今は今を大切にしてね・・。
|
|
大山 知美 30代 女性
東松島市野蒜にて被災
(平成24年9月5日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
野蒜小学校の体育館に入って、担任の先生に挨拶して、雑談してたんです。そのときは津波が来るなんて思ってないのでね。そしたら、津波が来るみたいだっていう話が聞こえてきて、校舎に移動した方がいいっていう感じになったんです。それで、子どもたちに靴を履かせて、下の娘2人に履かせたか履かせないかで、もう水が入ってきたんです。「あぁー」って思って、一番下を抱っこして、走ったんですね。奥のステージの方に行ったら、そこにいたおじさんが引っ張り上げてくれてね。ステージに上がったんですが、すぐに足が届かなくなっちゃって、「あ、やばい」と思って。当時3才の娘が右手にいて、左手に荷物を持ってたんですけど、荷物どころじゃないなと思って荷物を投げて。左手に5才の娘も抱いたんです。抱いたと同時に、私ももう足が付かなくなて浮かんだので、「お兄ちゃん、お兄ちゃん、どごいるー!」なんて言ってね。お兄ちゃんは、わたしのジャンパーの帽子にすがってて「背中で浮かんでる!」なんて言うから「ちゃんと帽子につかまっててよ」って言いながら、どうしたらいいんだろうと思って・・。皆さん結構、どんちょうとか、ああいうのにつかまって流されないようにしてたんですけど、私は両手がふさがってたのでそのまま流されちゃったんです。体育館の中が渦になってて、その渦に巻き込まれて流れたんですけども、運よく流れたのがバスケットゴールの方で。きっと渦の端の方を流れてたんでしょうね。「お子さん1人ずつよこしてー!」って言われて、ギャラリーの人が1人ずつ引っ張り上げてくれたんです。一番下から順番に渡しました。ちょうどギャラリーと同じ高さまで水位があったんですね。ギャラリーの柵って今思うと高いんですけど、あのときは「はいっ」って渡して、「はいっ」って受け取れるくらいの水位だったんです。必死でしたね・・ひとりずつ渡して、そして私も引っ張り上げてもらって。
そこまでは、一瞬だったと思います。5分も10分も浮かんでたわけじゃなく、あーって思う間に流されて、端っこにぶつかって、引っ張り上げてもらって・・。上がってからが長かったんですよ。子どもたちはもう、何があったか茫然としてて、「何が起こったんだろう、みんな浮かんでるよ・・」って。私は最初のほうに助けられたので、皆さんまだ浮かんでたんですね。「浮かんだよ」とか「沈んだよ」とか、子どもは冷静に見てるわけですよ。浮かんだ人がいるとか、沈んだとか、あの人は何回も浮かんできてるとか・・。みんなで、何かないか、ロープはないかって言ってるんですけど、下の子どもたちは「怖い、怖い」って言い始まったので、申し訳ないけど私は救助のほうじゃなくて、子どもと一緒にいようと思って。ぶるぶるぶるぶる震えてた子どもと一緒に、さすりながら・・。あとは、そこからはもう、ひたすら寒い寒いっていうのに耐えてたような感じです。
|
|
安倍 淳 50代 男性
安倍 志摩子 50代 女性
㈱朝日海洋開発 経営
(平成25年3月14日鹿島台の会社にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
安倍 淳
|
|
あの日、私はいつものように仕事をしていました。外に出て、みんなどうしてる、こうしていると話していて。そして1時間が経過したんですけど、その時、今思うとやってはいけないことの最たるものですよね、津波を確かめに行くっていう行為。津波が来る時は川の底が見えるんだと聞いていたもので、本当に津波って来るのかな、っていう事で、私と仲のいい地元の方と一緒に河口を見に行ったんですよ。川を見て、そんなに底が見えている訳じゃないから、津波は来ないな、と思いました。
でも、自宅の前に来た時に変な音がしたんですよ。ガサガサ、バキバキ、そういうのが混じったような音がしたので、「あれ、おかしいな?」と思って。新町の通りは幅があって見通しがいいので、ちょっと左側の河口の方を見たら、一番端に津波がぶつかって、波が返ったんですね。それが津波だってすぐわかったんですけど、嘘だろう、まさか、って思いがもう99パーセントで。あとは体が向いている方に走ったんですね。私はそのまま向かいにあった、8ヶ月前に建てた事務所の方に走ったんです。
3時50分近くには、僕らは津波にあったということです。2時46分の1時間後、ってことですね。凄い勢いで水が上がってきたんです。山の方を見たら、水が一面にあって、浜市方向を見たら、松の木の頭しかないんです。すごいな、とうろうろしていましたね。そのうちに、事務所の土台がバーンと外れて、動き出したんですよ。流れ始めると、隣の家にぶつかったりして、ぐるぐる廻り始めて、方向感覚がわからなくなりました。家内がいた自宅が自分より前にいて家内がベランダの端にいたのが見えたんですね。ちょうど、鳴瀬川と吉田川の合流点付近だと思います。たまたま、うまい具合に一瞬ぶつかったんです。それでも距離的には3~4メートル以上あって、がれきもあったんですけど。「こっちに、飛べ。飛べ」って言ったんですね。私は体を半分くらい乗り出して、手を伸ばして。家内はベランダを乗り越え、屋根を伝って、這って行く状態で、捕まえましたね。
JR仙石線の高架橋の下をくぐる時に、2階の事務所ごと、壁がついたまま激突しまして、だるま落としのように、くぐる時にすぽんと建物の屋根と壁が全部落ちました。残ったのは自分たちがいた3~4メートルのフロアだけです。その時、自分は水の中に落っこちたのですが、記憶にないんですよね。あばらが折れていたのも、全然気づかなかった。頭も打って、凄い衝撃だったんだね。そして、家内につかんでもらって、フロアの上に上ったんです。そのまま腹ばいになったんですけど、その時の言葉が「これが津波か?これが事務所なのか?」でした。40分~45分流されたんですけど、その言葉しかなかったですね。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
安倍 淳
|
|
今、自分が一番怖いのは、2年とちょっと過ぎて、あの時のことを忘れることですね。人間って忘れるようにできているから、それが一番怖いです。だから、いろんな所に行ってお話する時は、その当時のいろんなものを見て、その時の気持ちに返らなければいけないな、と思っているんですよ。後から付けた情報だと、あまりにもきれいに話してしまうじゃないですか。あの時って、汚かったんですよ。物もなかったし。そういうのを本当に伝えるには、貧しくないと駄目なんですね。物がなかったという物質的な乏しさがないといけないんですよね。今みたいに、冷蔵庫を開けたら何でも入っていたんじゃ、そういう話ができませんものね。
子どもたちには、どんな状況に追い込まれても、必ず自分が希望を持っていれば、物事は明るい方向に進んで行くんだ、っていうか、望む方向に進んで行くんだ、ということを信じてほしいんですよね。学校の5教科のように、いろんな専門的なことを学んでも、それは社会に出てすぐに役立つものではないから。仲間の中で生きる、ってことを勉強してほしいと思うんですよね。どんなふうになったって、マニュアルから外れたら死んじゃうようじゃ困るので。どんな時でも、人を信じるとか、自分の信念を持つ、ってことができれば、どこでも通用すると思うんですよね。その一貫として、水難事故のことを僕たちは教えられるので、教えながら、子どもたちと一緒に学んで行きたいと思います。
|
安倍 志摩子
|
|
自分たちは、全然辛いことなんてなかったと思うんです。今回のことで。無くなったのは、建物だけで、家族は無事だったので。それから、仕事もありますし。だから、仕事がなくて大変だったり、子どもを亡くしたり、家族を亡くしたりしている友達がたくさんいる中で、私達が辛いなんて言って、泣いたり、落ち込んだりしていられないな、と常々、戒めのように考えてます。そんなふうに思いを寄せることぐらいしかできないので。自分たちが頑張って、少しでも世の中のために出来ることを、例えば仕事を頑張ったり、いろんな話をしたりして行かないと。きれいごとじゃなくて、心底そう思うんですね。周りの人たちのことを思うと。本当に耐えられないような、辛い思いをした人たちが山ほどいる。だから頑張らないといけないね、といつも思っているんですけど。
私は、人間っていうのは、もっと力があるものだ、ということを信じてほしいんです。震災直後の避難所とか、何もないような所でみんなが生きてきたけど、みんなで協力して、希望が見えれば、いろんな力を結集して、乗り越えることができるんですよね。地震があったらすぐ逃げる、危険回避行動はもちろんなんですけど、その他に、人間っていうのはどんな極限状況でも希望は見えるんだ、持てるんだ、ということを信じてほしいな、と思うんですね。それを持てるかどうかで、乗り越えて行く力が左右されるんじゃないかな、と思います。
|
|
|
鈴木 大介 10代 男性
佐藤 一紀 10代 男性
かんぽの宿松島(東松島市野蒜)で被災
(平成25年5月19日東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
【質問】震災当日、どこで何をしていましたか?
(鈴木 大介)
あの日は卒業式が終わって、謝恩会でかんぽの宿にみんなでいて、食事をしていたら、地震に遭遇しました。それで、何があったかわけがわからなくなって。とりあえず逃げて、屋上に上がって外の景色を見てみたら、もう信じられないくらい、ぐちゃぐちゃで。車も流されていたし、人も流されるのを見てしまったり・・。それは、きつかったですね。
【質問】屋上から見た津波は未だに思い出したりしますか?
(鈴木 大介)
頭から離れないですね。一生離れないと思います。
(佐藤 一紀)
忘れちゃいけないことなので。車とか、いろんな・・人が造ったものが、こんなにも簡単に壊れるんだなって思いました。
【質問】翌日、水は引いていたんですか?
(鈴木 大介)
水はほとんど引けていたんですけど、泥とかがいっぱいあって、歩ける状態じゃなくて。けど、やっぱり一旦は家には帰んなきゃ、ってなって、歩いて家まで帰りました。
【質問】卒業生の中には、家には戻れず、そのまま避難所へという友達もいましたか?
(佐藤 一紀)
ほとんどですね。(家が)無事だったのは、3~5人くらいです。
(鈴木 大介)
俺も帰った日は家じゃなくて、避難所で1日過ごしました。大塚のコミュニティセンターで。家族みんなでですね。人がいっぱいで、区の人がほとんどいた感じですね。
【質問】夜が明けて、見た風景はどうでしたか?
(鈴木 大介)
ここには、何があったんだろう?というか・・。原形が留まっていなくて。信じられなかったです。何があったのか分からなくて「この震災、嘘なんじゃないか?」って思ったりしました。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
【質問】将来の進む道はもう決めていますか?
(鈴木 大介)
僕は就職希望です。震災中に消防士の方々にお世話になって、自分もこういう人になりたいな、って思って。公務員で消防になりたいな、って思っています。消防士さんって、火を消したり、体を使う仕事だけなのかな、と思っていたんですけど、避難所に来てくれて、苦しんでいる人たちの話を聞いてくれたり、カウンセリングみたいなこともしてくれて、こういう優しい方々が揃っているんだなぁ、って思って。それで憧れて消防士になりたい、って思いました。
【質問】これからの防災について、震災を経験して学んだことはありますか?
(佐藤 一紀)
親から聞いた話なんですけど、前のチリ地震の時に、津波はあんまり来なくて、それで今回、油断して流された人が多いということで。とりあえず、地震っていうのは震度がどれくらいで、マグニチュードがなんぼ(どれくらい)であっても、油断は決してしないで、常に気をつけて生活していくのが一番いいのかな、って思います。
(鈴木 大介)
一紀と一緒で、やっぱり油断しないことですね。津波は絶対来ない、ってみんな思っていたんですよ。前にも大きい地震があったりして、その時も津波が来なかったんだから、今回も大丈夫、っていう油断が。やっぱり油断しないで、常に、地震が来ても来なくても、気を引き締めて生活することが大切だなぁ、って思いました。
【質問】震災を経て、自分の中で変わったことはありますか?
(鈴木 大介)
中学校で一緒だった人達と、中学校の時以上に結びつきが強くなったかな、って思います。普段の生活で会う人がいるんですけど、会った時に気を使ってくれたり、優しいというか・・。中学校の時はもっとさっぱりした関係だったんですけど、いろいろ心配してくれたり、逆に自分も相手のことを心配したり。(部活で)怪我したって情報がすぐ広まって、そういう時はみんなが心配してくれたりします。みんなで同じ風景を見ているので、仲間っていう気持ちはそこから強くなりましたね。
|
|
木村 孝雄 50代 男性
野蒜市民センター事務長
(平成25年6月20日 野蒜市民センターにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
大きい地震の場合は津波のことを考えなければならないので、「来ないだろう」という前提はあったんですけども、山に逃げなさいということを言っていたものですから、小学校の高台へ地震が収まると同時に、妻と母親は避難をしました。私は店の片づけとかありましたので、そのままそこに残っていました。そして、来ないだろうけど1回、自分も避難しなくてはいけないということで、戸閉まりとかブレーカーとか下げて、市の防災無線を持って避難をしようとしたんですね。その時にラジオから「三陸、気仙沼で6メートルから7メートルの津波が到着している」という情報があったんです。「じゃあ、もしかしたら」ということで、私も外へ出たら東名運河の水が全部引いていて、底が見えていたんですね。それで、もしかしてということで隣近所に声かけて、「1回逃げましょう」というとこで、野蒜の高台に避難したということです。
それから、高台へ来まして。亀岡の地区センターの役員をやっていたものですから、避難訓練とかあるじゃないですか。いつもの通り、その時も津波はこないだろうと、ただ少しは長引くなということで、地区の災害本部を作ろうとみなさんで協力しながら、訓練通り作り、テントを建てようとしていたら、右の耳から凄い音が聞こえましたね。いわゆる瓦礫の擦る音、津波の音ですけども。山田そろばん塾ってあるんですけども、その右の方から津波が約2メートル以上あったですかね。真っ黒い津波です。ひたひたじゃなく、立って来るんですね、津波って本当に。壁ですね。それを見て、一目散に小学校の校舎に逃げました。ただ本当に見た時間がぎりぎりだったんですね。津波に遭わないでそのまま校舎に入りました。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
今、鹿島台にいますけども、野蒜を忘れましょうと簡単に忘れられるものじゃないし。今は迷っていると言いますか。今後どうしたらいいんだろうと。ただ、私はありがたいことにここに住まわせてもらって、いろんな方と知り合って、震災後に市民センターの職員になったものですから、まあ、何とか少しでも私がここで生きて、生活していた今までの御礼をしなくてはいけないなという気持ちでやってます。この年で、将来の展望がどうのこうのと、なかなかもう一回ゼロからスタートするのは難しいですね。逆に言えばまだまだですけども、残された時間っていうのを、それをどのように使おうかなと。
|
|
丹野 幸男 60代 男性
震災当時 市議会議員
(平成25年7月12日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私は、地域では常々、戻るなってことを言っていたんですけども、その時はまあ、慌てたんでしょうね、戻ったんですよ。洲崎に。一番大事なミスを一つ犯したのがラジオで津波の情報を聞かなかった、ってこと。全然わからずに、洲崎に「どうなってんだ」っていう思いで、向かったわけです。そしたら、途中で区長さんが顔色変えて「みんな出ろ、逃げろ」って叫んでいたのが記憶にあります。年取った方が洲崎に相当いますんで、区長さんに聞いたら「まあまあ避難したんだけど、まだ残っている」と。探したら2~3人いましたんで、道路に出てきたのを、野蒜小学校の体育館に送って行ったわけです。そこは市の指定している避難場所だったので、「ここで大丈夫だから、ここにいなさい」ということで。あと区長さんから頑固なお婆さんが一人残っているということで、報告があったんです。お婆さんを助けに行ってくるからと、再度洲崎に向かって行ったら、亀岡橋を過ぎて間もなくですね、パッシングする方がいて、何だろうな?ということで、「何だい?」と話したら、「津波がえんまん亭(洲崎にある食堂)まで来ているんだよ」ということで、すぐUターンしましてね。亀岡橋に向かったわけなんですけども、あそこは渋滞していましたね。それで田村理容店という所に車を突っ込んで、北大仏の仙石線のトンネルがあるわけですけれども、そこへ逃げました。
そして津波に呑まれたと。ちょうど右手に電車がひっくり返っていたんですね、仙石線の。ですから、瓦礫はあそこで止まったのかな?私がいた所には瓦礫は流れて来ていないんですよ。泥を3杯くらい飲みましたけども。あと、タイヤが浮かんでいたので、そこまで泳いで、タイヤにくっついていたんです。そこで3時間位浮いていましたね。暗くなっていましたから、もう。その2~3時間の間に何を考えたかというと、「もう、自分は駄目なんだ、死ぬんだ」と、覚悟を決めました。もう、誰も助けに来るわけじゃないし、もちろん自力で歩けるわけじゃないし。水ですからね。ただ、左手に若いお母さんが、生まれて1年もたたない子どもさんを抱えて、木にひっかかっているんですよね。そして「おんちゃん、助けて、助けて」と。助けるわけにいかないんですよ、動けないんですから。それを聞きながら、「頑張れ、頑張れ」ってことで、時間は過ぎていったんですね。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
何かしようかという時には仲間と一緒に、やれる何かをやりたいと。野蒜地区に世話になったもんだから。これは忘れることできないですね。3人の子ども、みんな学校出させてもらったんだから、旧鳴瀬町から東松島市にね。何かを恩返ししたいな、と思っています。自分でも人生変わりましたね。逆算するようになった。今までは、あと5年たったら70何ぼになるとか。あと、俺死ぬのは90歳くらいかな、と思っていたんだけども、自分の復興を考えた時に、今建てないと、俺は新しい家に入れないんじゃないか、って思ったの。あと何年生きられるかって仲間と話をするんだけども、「家建てることないよ。あと10年も住まないんだから」とかさ、「病気してあと2年位で終わるんだから、公営住宅に移った方がいいんじゃないの」とか。その方が楽ですよね、公営住宅の方が。でも、やっぱり自分の家に住んでいたものだから。1500坪平らな所だから、果樹園をやってみようかと、別の夢を探してね。孫と一緒に暮らすもんだから、その孫たちと一緒に、何を植えるか、りんごか桃かとか。そんなのみんな買って、果樹園を作ろうというような。子どもに返りましたね。果樹園を作りながら、仕事は現役で仲間と一緒にやれるところまで、精一杯頑張っています。まだ、やつれていませんから。疲れてっけどね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
皆さんがどう思ったかわかんないけど、想定外で決めつけないで、今後、復興するにあたって、よほど考えなければ駄目だな。自然には勝てないんだ、やっぱり。俺、つくづく思ったね。避難道路、あんなのなんぼ(どれだけ)立派なの作っても無駄。だからやっぱり、年とってる人は特に、10分位で高い所に逃れること。ビルでもいいし、タワーでもいいし。道路は無駄、私はそう思います。だってさ、避難道路作っても、一人が停車すれば終わりだよ、アウトだよ。皆、乗り降りしてね。だから、よほど考えないと。
本当に安心、安全なまちってどういうまちなんだ、って聞かれた時に、心とか何とかって、それも必要です。みんな仲良くいいまちを作って、コミュニケーションを大事にする。そういうのは大事だけども、災害に強いまちづくり、というのも大事。今鹿島台、大崎市でもやっていますけどもね。吉田川の堤防が決壊した時に、この町は守るんだよ、という堤防を作ったんですよ。道路をね。あれなんかもね、町長が発案したんじゃないかな。やっと今、完成なんだけども。町だけは水没から免れよう、ってことで。
ここだって危ないですよ。この間の津波で終わりではないんだから。千年に1回っていうんだけども、その1回が今来るかもしれないし。そこを、津波が来たって、逃げれば命だけは助かるよ、っていうまちづくりをしてもらいたい。家は流されてもいいから、命だけは助かると。そういうまちづくりをみんなで考えて。議員さんたちに任せないで知恵を出してね、そう思います、今。
|
|
黒沼 俊郎 40代 男性
宮城県松島自然の家
(平成25年8月8日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震がずいぶん長く続き、停電し、水道管が破裂し、机上にあったものが音と共に倒れていました。落ち着きを取り戻した時に、班長の指示で、それぞれの部署の確認作業をしました。主に宿泊棟と、当日は5つのキャンプサイトがあったのですが、どこにもお客さんはいないということでしたので、所内にいる人間の確認。外部から入っていた2人の業者の方も一応、ホールに全員集まりまして、情報を収集しようとしました。
ところが、何かで情報を入れなければと思ったのですが、ラジカセには普段から電池が入っていませんでした。エコ的な扱いもあったんでしょうが、貸し出しする時まで、敢えてはずしていたんですね。電池のある所に行ったら、そこが収拾つかなくなっており、どこに電池があるのかわからないような状態でした。何とか探し、電池を入れて電波を取れる所まで行きました。館内では、電波を取り入れることができず、建物を出て玄関前2メートルまで行ったところ、一番先に飛び込んできたのが、「大津波警報」でした。大津波警報って聞いたことがないなって、すぐ館内に戻り、館内にいた人全員に「大津波警報です」と叫びました。
夕立ちの直前みたいな感じで、どす黒い雲が流れ始めたな、と思ったような時に、バリバリバリという音がしてきました。私は、ちょうど1階付近にいたと思うんですけど「このバリバリという音、何だろうな?」って思いました。自然の家は廻りが木で囲まれているので、見通しが悪く、いくら屋上に上がっても海岸線は見えないんですね。でも、バリバリという音と共に、茶色い水がすーっと寄ってきたんです。「津波だ」って叫んで、2階の屋上に上がった時に、たぶんその時点で11人のうち8人位は屋上にいたんです。ところが、これもやんなきゃならないんじゃないか、と思っていた何人かが、自分の判断で1階の食堂付近か事務室にいたんですね。「津波だ」っていう声である程度みんなが我に返って、誰がいる誰がいないっていうのをとっさに判断し、一番最後に、たぶん事務の職員が階段をとんとん上がってきて、全員が確認されて「あっ」って思った時にはもう、さっきまで私が見ていた茶色い水がひたひたと来る感じではなく、たぶん1メーター、2メーター、3メーターと、ぐうーっと水が上がって来る状態でした。屋上に青い手すりがあって、野蒜海岸方面を見渡せる所があるんですけど、全員がそこにしがみ付きながら、水が増えて行く状況を見ました。
一晩、何とか体を寄せ合って寒さをしのぎ、翌朝を迎えたんですが、スタッフがまず男女に別れて次のことをしました。女性は、研修室にあった私たちが使った椅子を、屋上に持ち出して「SOS」の文字を書き、男性スタッフは木を集めました。ただし、周りの木はほぼ濡れているので、施設の中で生かせる木、乾いている木を集めて炎をあげました。つまり、「ここに人がいる」というのろしをあげました。その火を上げ始めて、食堂のスタッフが朝食の調理を始めようとした時だったと思うのですが、ヘリコプターが自然の家上空を旋回しました。いったん旋回して確認して、ちょっと時がたって、また戻って来て、「救出しますから、もう準備して下さい」と。班長から、「助けてもらえるから、動くぞ」と指示されて、みんなで屋上に集合したんですね。ヘリコプターから、救助のためのスタッフが降りてきて「これから皆さんを救助します」と、助けていただきました。
|
|
伊藤 洋子 60代 女性
(平成25年8月21日グリーンタウンやもと仮設住宅ひまわり集会所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私は石巻出身なのですが、地震があったら「津波」っていうのは、親にも言われてきましたし、一応は知っているつもりだったんです。だけど、あそこまでの津波っていうのは、いざとなるまでは考えられなかったです。野蒜って言っても、家は駅の後ろ側の方でしたし、海から来ると松林があるし、運河があるんですよね。さらに向こうの山の根っこだから、そこまで来るとは想定していませんでした。地震で家もかなりやられましたけど、避難しようって気はなかったですよね、そもそも。
地震と同時に、たぶん防災無線が落ちたんでしょうね。だから、外で津波が来るっていう知らせは全く聞いていなかったんです。隣のお婆ちゃんが「津波が来るから避難しろ、って言うんだけど、どうする?」って家に来たんです。「どうしようね。鍵、閉まんないのよ」って言っているうちに、ごーっと鳴ってきたので見たら、前の家と家の間から何か黒い山みたいなのが動いてきて「えっ、ひょっとしてあれ、津波?」って思った時はもう、ほんの近くまで来ていました。
隣のお婆ちゃんを抱えて2階に上がった途端に、隣のお婆ちゃんの家は流れて。自分の家は浮きあがって、2階に乗ったまま流されたんですよ。2階も再び水がきたので腰までは濡れたんだけど、窓枠に乗ってカーテンにつかまって、それで流されたんです。何分くらい乗っていたのかよくわからないけど。周りの景色も変わるしね。必死でしたし。
その後、着地したんだけど、それがどこなのかよくわからなくて。でも、前に浮いていた車が、だんだんタイヤが見えてきたりしたので、水が少なくなったんだろうな、と思うくらいまで、その家で待ったんですよ。そこで、どうしようかは悩んだんですよ。前の家まで泳いで行って、助けを求めようかとか。でも、あそこの家の2階にどうやって上がろうか。その家に一晩居座ろうかとか。でも、取りあえずここまで濡れているから、隣のお婆ちゃんがこのままでは凍死しちゃうから、避難所までは行かなくちゃならない。水が引いたような状態を見て、行かなくちゃならないね、と思って歩き始めたんです。だけど、地面は平らなわけないですよね。津波の後だし、しかも瓦礫だし。だから、2歩3歩歩くまではよかったんだけど、何歩か歩いたら、ぐーっと沈んじゃってね。すっかり濡れたんです。それで進めなくて、進めなくて。瓦礫をまたぐしかないですよね。隣のお婆ちゃん、ダウン(ジャケット)まですっかり水を含んでいるから、這いあがれない。それを押し上げて、自分もくぐろうか?またごうか?と、繰り返しながら行っているうちに暗くなって。3時間か4時間くらいですかね。野蒜小学校の近くに赤色灯が見えるので、たぶんそこまで行けば、避難所だから何とかなるだろう、と思って頑張ったけど、途中までしか行けなかった。お婆ちゃんが力尽きて。このままでは駄目かな、と思っているうちに「もう、駄目」って言って、倒れちゃったんです。喋らなくなって。「このままじゃ、私も駄目かな」と思って、「とりあえずどうしようかな」と思った時に、近くにあった2階。まあ、真っ暗で見えないんだけど、人がいそうな気配がしたのね。それで「助けて下さい」って騒いだら、「誰?」って。その人が何件か横の人に声をかけてくれて、そこからさらに電話が通じないものですから、大きい声で「助けてやってくれ」っていうのを、つないでつないで、中継しながらその消防団の人まで届いたんでしょうね。何分かして、助けに来てくれました。先に隣のお婆ちゃんがぐったりしているのを連れて行ってもらい、「奥さん大丈夫ですか?」と言われて「大丈夫です」って言ったんだけど、あと記憶がない。気がついたら石巻赤十字病院にいました。点滴されている時に気がついて。次の日になる前、日赤がものすごく混んでいたんですよね。元気になった人から、ベッドじゃなくて床に降ろされたのね。床が妙に温かかったです、床暖があって。日赤の毛布1枚なんだけど。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
人から見ると、ものすごく辛くて、生きていることが奇跡みたいに言われるけど、自分ではまだそれはわからない。だから、何かするたびに、「(家に)あったな」と一瞬思うのね。でも「あっ、(津波で流されたから)ないんだ」と思い返すんだけど。それに代わる何十倍、何百倍もの物をいただいているから、今はあまり物欲はないです。だから、物が欲しいんではなくて、来てくださることが感謝、ありがたいと思います。まだ、来てくださるでしょう。2年半にもなって。ありがたいことです。
ここの集会所って、ものすごく行事活動が多いんですよ。その準備と片づけまでやるものだから、1つの行事があると前の日と次の日まで、いろいろやることがあるものだから、気が紛れる。楽しいですよね。夏祭りをやるっていっても、業者さんに頼んでの既成のお祭りじゃなくて、ここは全部手作りで、自分たちでやりますから。残っている人達は、できるだけここ(集会所)に引きだして、楽しく。ずっといるわけじゃないでしょ。あと2~3年ね。楽しい仮設の生活っていうのも少ないのでしょうけど、でもいるからには楽しくやっていきたいでしょ。だから、そういう事をわざわざ作って。
|
|
今野 みい子 60代 女性
職場(東松島市小野)で被災
(平成25年8月21日 グリーンタウン仮設集会所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震の時は仕事場にいました。松島洋装(小野字鍛冶沢)で仕事中でしたが、工場が広いので、棚に並んでいた糸とかが倒れてきたんです。布を裁断する長い台があったので、みんなに「台の下に入りなさい」と言ったのですが、みんな慌ててしまって、泣いたり「怖いよー」と言ったりしていました。私は、ちょうどその裁断台の下にいたんですけど、結構大きくて長い地震でしたが、この下にいれば大丈夫だと思いました。
そこには、50人から60人くらいいました。揺れが収まるのを待って、3人の娘に電話をしたのですがつながらなくて、最後に1回だけ電話がつながったんです。その娘は小野の駅のほうに住んでいて、孫が浜市小学校と牛網保育所にいるので、子どもたちを迎えに行って、と頼まれました。娘は石巻で仕事をしていました。一度だけつながった電話で、私はそちらに行かなきゃ、と思いました。
小学校に着いてから、初めは上の子を連れてくるだけだから、下の孫には「車で待っていてね」と言って、迎えに行こうかと思いました。でも地震の後で孫も不安かなと思い、一緒に迎えに行きました。かばんは車に置いて、車のカギと携帯だけ持って行きました。そうしたら先生に靴のまま上がるように言われ、2階まで上がりました。2階に行ったら「来たぞ、来たぞ」という声がして、ふっと見たら、津波が2階の高さで来ていました。ここじゃだめだとなって、3階の視聴覚室まで急いで上がりました。そこは部屋が小さくて、住民、小学生、迎えに来たお母さんたち、合わせて400~500人くらいいたんですかねえ。全員で狭い所に一晩いたんですけど、トイレはないし、水もない、電話もつながらない、食べるものもない、という状態でした。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
私の主人は介護施設でお世話になっています。この仮設の集会所がこういう形で開いていなかったら、もっと寂しかったでしょうね。幸いスタッフ4人で交代して来ているので、何とか楽しく暮らしています。隣近所の人との付き合いも、結構楽しい付き合い方ができているので、今はいいかなあ、と思っています。こうして、物作りをしていると、「おはよう」「こんにちは」って、来てもらってお話できていることがいいかなと。毎日一人で何もしないで家にいたら、しゃべらないでしょ。話ができないし、足腰も弱ってくるでしょ。結構、笑って楽しく過ごしているので、それがいいかな、と思います。
|
|
板宮 良子 70代 女性
(平成25年8月21日グリーンタウンやもと仮設住宅ひまわり集会所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私は仕事で、宮戸の里浜に行っていたんです。宮戸で被災して、8日間宮戸小学校に避難しました。ちょうど、海苔の仕事で行っていたものだから、今日で終わりだねと言っていたのね。「今日で終わりだから、明日からゆっくりすっぺね(しようね)」と言っていた矢先の、あの地震だったから。もう機械は止まらない。どうして、こっから逃げっぺ(ここから逃げようか)っていう感じで。
やっとの思いで外に出ました。あそこ(里浜)の人達は「ここには津波は来ない。大丈夫だから」と、そういう状態でした。でも、「この地震だから、津波が来ないってことはないと思うよ」と、下の漁協の前で30分以上いましたね。1回は大高森に逃げたんですよ。大高森に上がって、見ているうちに「津波が来そうもないから」って下さ降りてきて、10分か20分位は下にいて話していたんです。
そうしているうちに岸壁を見たら、1メートル位の堤防から(津波が)上がってきたのが見えて、それから又、大高森さ上がったっていう状態で。それでも、「家に帰ろう」と。30分位してから、津波が収まったから「帰るにいいかね(帰ることができるかな)」なんて言って、帰ろうと思ったら橋が折れていたんですよ。野蒜と宮戸の間の松ヶ島橋。あの橋が折れて、折れたからもうどこにも出られないよと。そこでもう、足止めをくらったわけだよね。
それから8日間、宮戸の小学校でお世話になってきました。連絡を取ろうにも、取れない。だけども、津波の2~3日前かな、お父さんと話をしていたんです。「もし、私が仕事で宮戸に行っていたら、絶対、迎えに来ては駄目だよ」って。「何があっても、迎えに来ては駄目だよ」って、そう言っていたから、迎えには来なかったんです。矢本の中学校に行っていた孫を迎えに行ったので、うちではお父さんも助かる。お陰様で子どもたちも全部助かりました。
|
|
横田 浩子 40代 女性
ヘアーサロンヨコタ 店主
(平成25年9月4日グリーンタウンやもと仮設ヘアーサロン・ヨコタにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は、たまたまお客さんはいなくて、旦那が一人で店にいました。私は隣のお店に買い物に行っている最中に地震が来たんです。あまりに大きい地震で、自宅を外から見た時に、網戸が踊りを踊っている感じで「これはただ事じゃないな」と思い、取りあえず家に戻りました。茶の間にいたおばあさんと娘を確認したら、凄い錯乱している状態だったので、落ち着かせて。おじいさんが、川向いの公民館に行っていたので、安否を確認したら大丈夫だということで。一番下の子は学校から帰ってきていなかったんです。当時、高校1年生の娘と、中学1年生の息子が一緒に自宅にいました。
外に出て、運河を見たら、水が半分くらい減っていたけど、干潮だとそのくらい減るので、「たいしたことないね」と言ってたんです。そうしたら、消防の人が回って来て「津波が来るから避難して」と。「放送(防災無線)も聞こえてないから、大丈夫」と言ったんだけども、「とりあえず、避難しろ」と命令が出たので、家に戻りました。体が不自由なおじいさんおばあさん(義父母)がいるので、野蒜駅の裏に山があるから、そこに避難させようと思って、家を出したんです。服を着て、貴重品を背中にしょって(背負って)。
そうしたら、たまたま近所の方が来て「避難するんだったら、今、小学校に行くので乗せていってあげますよ」って言うので「じゃあ、お願いします」と。山を登るより車の方が楽なので、お願いして「あとから迎えに行くね」って。車には、おじいさんとおばあさんと、一番上の高校生のお姉ちゃんが乗りました。
旦那は店を片づけて、私は2階の自分たちの部屋を片付けようとしていたら、息子が「変な音する」って。「津波!」って言われて。とりあえず2階に駆け上がったんだけど、2階でもまずいから「屋上に上がれ」って。そして屋上からずっと津波を見ていました。ちょうど、家から新町方面の川の方を見ると山があって、その上に松の木がいっぱい生えているんだけど、その松の木を越えて黒い波が来たので「これ、もしかしてアウトかな」って思いました。ある程度になったら、水が収まって。収まってから、別の所に避難したんです。
息子に「水が引いたから、避難するよ」って声を掛けられて、貴重品を背負って、一人一人毛布を1枚ずつ持ちました。小学校に行こうとしたら、駅前は全く動きが取れない状態だったんですよ。駅裏から小学校にまわろうかと行ったら、裏も全然歩けない状態で。山の方に人がいて「上がって来い」って言われたので、そこで一晩野宿しました。野宿でも、30人近く避難している方がいたので。子どもたちとお年寄と怪我をした方は、掘っ立て小屋みたいな中で。動ける私たちみたいな人は「とりあえず、外にいろ」って。そこで火を焚いてもらって。飲み食いはできなかったけれど、鍋があったので火を沸かして、雪を溶かしてお湯にして、湯呑茶碗1個でみんなで1口だけね、と。それで一晩明かしました。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
震災後に、京都の方々が来てトラックに乗って、「散髪隊に行くよ」って。一番最初に出向いたのが蛇田小学校だったんです。それから釜小学校に行って、一番遠い所で狐崎まで行ってきたんです。あのまだ道路が普通じゃない時に。でも荻浜まで行くと道路が畳なんです。みんな陥没していて、畳の上をワゴン車で走らなきゃなくて。そっちこっちに家は倒れているし、消防車も倒れているような所を見ながらの運転でした。私たちは髪を切るだけで、京都から来た人たちはシャンプーを担当するからと。そういう流れで1週間くらい。最初の頃は子どもたちも連れて行ったんです、車の中で待たせて。蛇田小学校に行った時は校長先生が元鳴瀬二中にいた先生なので、すぐに会いに行ったんです。石巻だから、私たちは全く知らない人たちばっかりなんですよ。でも、石巻の床屋さんも一緒に行っていて、全部で5人くらいなので、自分のお客さんは自分でやりたいと。私たちは他のお客さんをやる、っていうので、結構人数はこなしましたね。狐崎に行った時は、夕方4時になったら「早く帰っていけ」って言われて。万石浦の橋が冠水すると、乗用車は無理だから、今帰らないと帰れなくなるから、と心配してくれたんですね。怖い面もあったけど、楽しかったね。
|
|
亀谷 伸 50代 男性
仕事先(仙台市)で被災
(平成25年9月4日 新東名自宅にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は仙台にいて、五橋の事務所に寄ろうかどうかと思った時でした。なんか胸騒ぎがしていました。やっぱり帰ろうと思って、新寺小路(仙台市若林区)を走っていた時、地震がありました。前の車がダンプだったのですが、揺れで車が浮き上がっていました。信号もすぐに止まり、新寺小路からバイパスに抜けて、東インターのところまで来ると、高速道路はもう通行止めでだめだということで、45号線に向かって、そのまままっすぐ、産業道路を来れば津波に巻き込まれると思ったので、すぐ45号線から塩釜の山の中を縫うようにして、利府に出たころは、車も渋滞になっていました。
ここ(東松島市)に着いたのが4時半頃でしたね。雪も降っていました。第一分団大塚部の団員がそこに(松島公園線)出ていまして、通行止めにしていたんです。「なんだ、この水?」と思うような塩水が来ていたものですから、私はたまたま、別の車で歩いていた(移動してた)ので、「ご苦労様です」と声をかけると、「亀谷さん、中には入れないよ」と言われたのですが、「だめなんだ。おれ、資材置場も堤防も見ないとだめだから。」と無理矢理入ってきたんです。でも、坂の上まで来て動けなくなったんですよ。雪は降ってくる。人は流されてくる。野蒜側を見て左の方から、人が流れてくるんです。昔、学校の先生をしていた、知っている人でした。もう1人、親戚にあたる人が、居酒屋のマスターをやっているのですが、流されて跨線橋の下に立っていたんですよ。「おおい。何してるの?」って言ったら、「いやあ。流されてここまで来た」ということで、あちこちにいた人3~4人でロープを投げて、引っ張りました。
流されてきた人を歩道のところに引き寄せて、かぶせるものも何もないもので「ああ、だめかな」と思ったんですが、一晩車にいました。うちの家内も事務所にいたはずだから、もう1人の事務員で七ヶ浜に嫁にいった女の子と、もしかして2人でいたかもしれないなあと思って。消防の長靴が車にあったので、どうにかして行こうかと思ったのですが、どうにも前に進めなくて。電話しても通じないし、私の車の後ろに消防の仲間や知り合いがいて、「おらいのうぢ、どうなってんのがなあ(私の家は、どうなっているのかなあ)。」とか「俺も、女房とも従業員とも、電話もできねえんだ。」とか話していて。とにかく車で待つしかない、と思っているうちに、消防団の団員の一人が、跨線橋のすぐ下から降りて行くところに家があるんです。「亀谷さん、家に来ない?」と言われ、「水、入ってっぺや(入っているだろう)」と言ったんですが、開けて入ってみたら、床の下まで水は入っていても、畳は大丈夫だったんです。そこに2人で雑魚寝しながら、一晩話しながらいました。
朝4時半頃、その辺をうろうろしました。水も結構引いたなあ、と思ったのを覚えています。長靴をはいて、家の方に入っていきました。すごい状況でした。がれきの上をこいで、なんとか歩いてきたら、家内が自宅の2階にいたんです。家内に聞けば、東名の跨線橋を越えた線路の向かいに実家があるんですけど、そこにいるおばあさんが心配で、迎えに行こうとしたところを津波にあって、車を持っていかれたようで。2階に逃げて、一命を取りとめたようです。2階には見たことのない人が7人か8人いました。家の前の電信柱のところに車が2台流されてきて、その中にいた人たちが、消防団の部下の奥さんと子どもたちでした。あとお父さん、お母さん。6カ月くらいの赤ちゃんもいて、低体温になっていました。うちの家内が連れてきて、みんなを中に入れたようです。もう一組は、塩釜から大曲に帰る途中に震災にあって、一晩泊まったようです。私が帰って来た時、知らない人が2階から手を振っていたので、家内もいるんだな、と思いました。
|
|
櫻井 けい子 50代 女性
(平成26年3月4日 図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
震災当日は、息子と一緒にちょうど山王の踏切渡る手前で地震になったんです。その時息子が運転していて、揺れたから「何、冗談やっているの」と「いや、冗談じゃないと」言われて見たら、電柱が揺れててこれはただごとじゃないなと思って、とにかく3番目の息子を迎えに行かなきゃないという頭があったので、ここに止めるわけにいかないからとにかく走らせて。山沿い利府街道を来て湯の原通って45号線に出て、松島のコメリの所から入って行って手樽に出たんですよ。それから富山に行って、富山の古浦あたりでちょうど海沿いじゃないですか、あそこで前の人に「津波来るらしいから、行かない方がいいよ」って言われて。そのままUターンして今度また富山まで行って、富山から45号線抜けてずっと行ったら吉田川もう逆流してたんですよね。「これ、もしかして逆流してる?」って、もう恐ろしくなりましたね。45号線からずっと下って来て浅井に抜ける道路に入って、中下あたりまで行ったら知っている人がいて「行かない方がいい、車置いて行った方がいい」って言われて。そこから3人で家まで走りました。
その時、夕方5時にはなってたと思うんですよ。野蒜小学校の校庭には、いっぱい瓦礫やら何やら入って来てたから、津波きた後だったんですよ、たぶん。自宅にはたどり着かないけど校庭から家が見えるので「あっ、家がある」と思って、私のは母はどこも悪くないんで「近所の人たちと一緒にどこか小学校が避難所なのでそこにいるか、家の2階にいるかとにかく大丈夫だろう」と思っていたんですね。寒いから、車置いていた中下の公民館に戻ってその時で6時過ぎてたんだよね。そこから定林寺に行って、駐車場に車置いて本堂の手前の会館に入って、ずい分いましたね。何百人っていたんでないかしらね。夕方中下の人達が、区長さんのご配慮があったと思うんですけど作ってくれたおにぎり、一膳の握り飯じゃないけどもあれが嬉しかったですね、本当に。あの味まだ忘れられませんね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
これから、高台(野蒜北部丘陵団地)に戻って来られると思うんですけど、亀岡の人達、またみんなでいろんな集まりをやりたいなと。亀岡だけだったんですよ、運動会とかスポーツ大会、夏祭りもやってたのは。そういうのをやれたらいいなと思うし。とにかくみんなが集まる機会っていうのを多くしたいなと。みんなで「あーよかったね」って笑っていられるようなそういうような。また前のように戻したいですね。亀岡は今在宅50件くらいしかないけども、また高台に戻って来られる方も何人かいるって聞いているので、その人たちでそのままいろんなことやれたらいいなと思いますね。前の亀岡みたいにやれたらいいなあ。けっこう亡くなっている人も多いんですけどね。年配の人が亡くなっているんですよね。また同じような亀岡にしたいです。どこまでできるかわからないですけどね。
この間、パドル(体操)で陸前高田に行ってきたんですよ。山の奥の奥で80歳以上の人達しかいないんですけど、その中ですごいパワー感じてきましたよ。あの年齢でもけっこうやれる人たちはやるなと思って、元気です。「俺まだ大丈夫だ。べこ(牛)飼ってんだぞ」って。そういうのを見ると、まだまだやらなきゃないよね私の年齢だと、と思うんですよね。ようやく震災の時の津波が見られるようになりましたよ、泣けますけど。うちを片づけに行ってその周りを見てきたことが全然なかったから。うちを片づけるのが精一杯で、12月に帰ってからようやく自転車で、「こうだったんだ、ああだったんだ」と見て歩ったから、それまでやっぱり見れなかったですよ。「おっかない」って。津波は見てないけど、川の逆流しか見てないんだけど恐ろしい。お世話になった定林寺には碑を建ててもらったし、母の名前刻んでありますよ。
|
|
佐藤 善文 70代 男性
避難所「佐藤山」の開拓者
(平成26年8月4日 佐藤山にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
この山を作ったのは、15年前です。平成11年あたりから作りはじめたんです。藪で全然人が入れるような状態でなかったので、1人でこつこつと作りました。この小屋作った時は、最初はこの辺の人達みんなからは「津波来ないよ」って言われたんです。こういうのを作ると、みんな車で来てゴミなんか持って来て、迷惑のような話されたのね。それでも、私は津波が来るっていう予感してたし、タクシーで人命預かっているから、人の命守るっていうのは事故起こさないばかりでなく、災害の時も人の命守らなきゃならないというので、ここをやり出した訳ね。「何で作ったの?」とよく言われるんですけど、チリ津波も経験してるし、金華山沖に断層があるから危険だと言われてたから、私ら尚更海の側で営業やっているもんだから、避難所が必要かなと思って。この材料は実家から持ってきて、だいたい3年位でできたんです。
避難道路が、野蒜駅から上がる道路、住宅から上がる道路、と方々から全部登れるようにしてあったから、一気に津波来た時、みんな上がってこれたのね。ここに向かって来た人たちは、一人も亡くならないで全員助かったわけ。怪我人やずぶ濡れになった人はいたんだけど。歩けない人は、おんぶされて皆上がって来たような状態でね。私が上がって来た時は、ここの小屋は一杯になってたんだけどね。 震災の時、ガスもストーブもあったから助かったのね。30人いたんです、ここに。みぞれは降るし、寒くて寒くてね。ストーブ2つつけてね。外国人もいたらしいですね、中国人だかも2人ここに上がって助かったとかね。ここで2日目くらいまで、情報入らないから、周りで亡くなった人いるっていうのわからなかったのね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
今JRの線を外し、サイクリングロードにしたらいいという案も出ていて、その場合海岸の方の避難場所はここしかないから、その時は協力してもらいたいというのが1つと、閖上から気仙沼まで桜をたくさん植えたんです。これは桜ロードって言って、これは残したいと言ってるわけね。仙台から海岸来ると、何かあるとやっぱり途中で休む場所はここしかないんだって。いろんな団体は、ここは注目しているわけね。
(人が)亡くなった場所は、どうして亡くなったか、人命が助かった場所はどうして助かったか、両方調べなきゃないと思う。研究する余地はあると思う。将来、海に海水浴や釣りに来て、津波来たらどこに逃げるか。高台まで逃げられないから、海岸の近くにこういう所残しておかなければならないと思います。
|
|
東名ふれあいサポートセンター はまぎく会
(平成26年8月4日 東名ふれあいサポートセンターにて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
会の名前は「はまぎく会」と言い、震災前から東名地区の老人会の集まりです。男女30人位いて、集まって旅行したりしていたのですが、今は震災で皆散らばってしまいました。野蒜や東名を離れてしまっても、鳴瀬の広報が毎月皆さんの手元に行くわけなんですね。その広報で呼びかけで新しく入ったメンバーと、前からいるメンバーがいます。去年の1月にセンターができて、みんなで楽しくできるようになったのです。それまでは、皆さん孤立していて、家の中に閉じこもってました。
活動は1週間に1回で月曜日にやってます。みなさん、それを楽しみにして来ています。皆さんは、元々東名だったのですが、今はそれぞれ多賀城の方、高城から二人、あと東名、この男性の方は大田区の人で。彼はここがオープンしてから、3ヶ月後から東名にずっとボランティアで来てくれていて、今も生地とか綿とかネクタイとか、いろんな物を支援していただいて、今日はたまたま休みだったので遊びにきてくれたんです。その生地とかは、大田区に住んでいた頃に、地元の仲間とか、小学校・中学校の頃の友達とかからいただいたり、ボランティアやっている時に知り合った方に呼びかけをして集めました。
生地は大田区さんとか、栃木とか秩父とか京都の方から来てます。いろんな方から支援していただいて、こういう物(つるし雛)を作ってます。綿も支援で頂いて、着物の帯地もです。今日のメンバーの他にあと3人いますが、都合で休んでいます。作った物は、来年の3月8日にここでひな祭りをやるので、つるし雛を飾って、地域の子どもたちに振る舞うんです。プロジェクトの方が来て、女の子に着物をレンタルで着せて、ひな祭りをしましょうという企画を出していて、これを作っているのです。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
このセンターができて、会長がいろんなことしてくれて。自分の家も流されたのに、返りみないで東名地区のために、うんとしてくれたの。こうして集まってこれたのも、会長さんと地域の方の協力だと思ってます。私たち、大田区さんが来ると家族同様です。この震災で、人のありがたみ、ここまでしてくれるっていうのを感じました。何にも言わなくても、気持ちをくんでくれて「こうだね、ああだね」って、大田区なんて高校生まで来てくれました。何かあった時に返せるのかしらと思うんです。私たち年配の人たちは、体では動けないので、何か身近にあるもので、自分で持っている物を差し上げれる物は差し上げたいと思います。そういうのは協力したいと思います。
|
|
奥松島観光タクシー
佐藤 輝弥 50代 男性
佐藤 礼子 40代 女性
(平成26年9月25日 奥松島観光タクシー事務所にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
佐藤 輝弥
|
|
あの日は、らくらく号「デマンドタクシー」の運転をしていました。小野駅前のミニストップさんで待機しているところでした。突然の揺れで、車が両脇に止まっていたのですが、揺れが凄くて隣の車にぶつかるんじゃないかと思われるくらいで、車から降りるにも身動きが取れないような状態でした。お客さんは、運行と運行の合間だったので乗せていませんでした。揺れが収まってから、次のお客さんの配車の予定があったので、病院に迎えにあがりました。看護師さんに「回せるタクシーをいくらでもいいから、回してくれないか」と頼まれたのですが「これだけの揺れがあったので何台来れるかわからないけど、連絡は取ってみます」とお話はしました。
それから私は、乗せるべきお客さんを乗せて行ったんですけど、お客さんを下ろした後に西福田の目移(めうつり)という所に、小さな橋があるんですね。南郷の方に抜ける橋なんですけど、その橋が段差ができていて、何らかの登れるような工作をしないと車はそのまま通行できないような状況になってたんです。向こうから先は完全にアウトだなと思いまして、連絡するにも電話もついているんですけど、当然通じませんので、市役所に行ってお願いしてみようと鳴瀬庁舎に寄ってみました。職員さんが対策についてお話されている最中でしたので、こちらの方のお話をするのははばかれたものですから、福田の方の道路状況は厳しいということを伝えました。
連絡取れませんので、私は会社に戻ろうということで、鳴瀬庁舎から鳴瀬大橋を渡って中下堤防ですか鳴瀬川沿い、吉田川沿いを河口の方に向かって走って行ったら、川が完全に濁って台風で大雨降ったあとで、鳴瀬川が氾濫するような危険な状況のその逆バージョンっていうんですか。河口に流れて行くんじゃなくて、河口から上流に流れて行っているような感じに見られたんですね。「これが、津波なんだな」と思いつつ、事務所の方に戻ろうとしました。事務所に入ってくる踏切が遮断機が下りっぱなしで、まるっきり通れない状況だったんですね。そこを運行している最中に、ラジオで大津波警報が出てるということだったので、会社の方に無線を入れました。
|
|
佐藤 礼子
|
|
前あった事務所の中で、仕事(配車番)をしてまして、揺れが始まった時は犬と一緒に一人でいました。建物自体が古かったせいもあるんですけど、あまりにも揺れがひどくて建物がつぶれるんじゃないかと思ったくらいでした。犬を抱いたまま半分建物の中、半分は外に出て「いつ終わるんだろう」と思いながら、揺れがあまりにも長かったので「これはおかしいな」と思いました。
(娘を)小学校に迎えに行ったら、みんな体育館に集められてまして、引き取りに行った時点で娘はもう泣いてたんですね。でも、私が迎えに行ったのは早い方だったみたいで、まだ待機していたお子さんもいっぱいいました。引き取って帰ってきて、「ランドセルを家の2階に置いてきなさい。いろいろ倒れていて危ないから、靴はいたままでいいよ」と言い、事務所に戻ってきたんです。義父と「すごかったね」と話していたら、ちょうど社長(輝弥さん)がタクシーで事務所の前に止まったんですね。その時、外に出ていた義母が「大変だ、波が来ている。津波だ津波だ」というので、びっくりして見たら線路の辺りが、水がザアーと来ているんじゃなくて、ぶちゅぶちゅとしてたんですね。社長が前に乗り付けたタクシーに、みんなで乗り込んで逃げたんです。逃げて行く最中に見たら、黒い壁みたいな高さが2メートル弱の波が、ずーっと押すように来るのが見えました。
山の斜面を登ってそこで見てたんですけど、家とか車とかいろんな物が流れてきて、娘を迎えに行ったさっきまで乗っていた車が流れて行くのが見えました。自宅の脇に車庫があったんですけど、その中にあった車がダフーと水に浸かって、クラクッションがずっと鳴りっぱなしでした。あちこちでいろんな所からクラクションが聞こえるんですけど、「助けて」と言って鳴らしているのか、勝手に鳴っているのかそれの区別がつかなくて。斜面に登った時他の人も一緒に登っていたんですけど、一緒に登ってた方のご自宅が見えるんですけど、そこに水が流れていって「娘が家にいる、無事だといいんだけど」と心配されていたんですけど、どうすることもできなくて。あとからその娘さん、亡くなってしまったんです。
あの時、目の前に社長が車で帰って来なかったら、あと義母が津波に気づかなかったら、誰も気づかなかったので、たぶん流れてたかなと・・・本当に偶然なんですけど、社長ももし間に合わなかったら、途中で車ごと呑まれてたと思うんです。
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
よく、お客様のお陰でとか、地域の皆様のお陰でとかいう言葉がいろんな商売やっている方から言われますけど、実際私らもその通りでですね、今回も私らが動いたことによって、すごい喜んで下さるお客がいる。どうでもいい仕事ではないってことで、誇りに思ってます。より安全な運行を提供していければなと。観光タクシーが走ってて良かったと、うちのタクシーのカラーがけっこうイメージが強いようでですね、お客様からすると昔の風景の1つのようなんです。野蒜周辺すべて無くなってしまいましたけど、野蒜駅に待機しているとか宮戸島を走っているとか風景の1つだったわけなんですね。そういう風景を残していくためにも、頑張っていきたいなと思います。
|
|
伊藤 礼子 40代 女性
野蒜西余景で被災
(平成26年11月6日 図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私は野蒜の西余景の、友達でもあり仕事関係のお客さんでもあるお宅にお邪魔してた時に地震が来ました。その友達は臨月を迎えた妊婦さんだったんです。息子の同級生の子どもさんが帰ってきたところだったので、とにかく「テーブルにもぐれ」と言って。妊婦さんと子どもを守るのが、私しかいないと思ってしまったんですね。まずレースのカーテンを閉めて、何か飛んできたら危ないから外の状況を見れるように、レースのカーテンを押さえてて、とにかくこの二人を守らなきゃという気持ちで。揺れながらも友達に「毛布2~3枚持ったほうがいいよ。長丁場になるからね。」という会話もしているんです。揺れてる最中だと思うんですけど、お互いの子どもたちが保育所、うちの息子が小学校で「どうしようか?」と。小学校に逃げるという頭で2人ともいるので、私が小学校の息子を迎えに行って友達に保育所は連れてきてもらおうかなという話もしてるんだけど、「いやお互いの子どもを守ろう」という話になって、それぞれ行動しました。
(野蒜)小学校の所はもう渋滞でした。体育館入る所に車止めがあって、誘導している人に「この車止め取らないと、亀山の方にずっと上って行って渋滞するから取らなきゃならないですよね。とにかくここの校舎に入れなきゃないですよね」と。1本道しかないわけだから、渋滞するのは目に見えてますよね。そこの車止めが外れなかったんですよ。だからもう駄目だと思って先生たちは体育館に行く、あと何人位父兄がいるとか教えてもらわないと私もわからないので、一人若い先生が来てくれて。お母さんたちも何人か来るんです。「こっち行くと渋滞だから、こっちこっち。ここしか入れない」って。体育館が避難所だから「ここから入れ!入れ!」と誘導しながら行って。あと先生が「もうこの位で。あとだいたい全部来たと思います」って。とにかく必死に保育所の子どもたちをと思ったんですね。
体育館に戻って、そこで「津波だ!!」と聞こえたんですね。ふと、見たらすごく静かな感じで「あれ?」と思ったら、遠くから「ぼ~」と静かに聞こえて、作業着着た人が2~3人真っ直ぐ走ってきた人と、曲がった人がいたんですね。曲がった人はどうなったかわからないけども、その人達の後ろに大きな建物だと思うんですけど、ぷか~ぷか~と来たのでスマトラの津波をテレビで見てたので、津波ってひどいとこの位になるんだと思ったので「津波だ!逃げろ!!」って言って、校舎しか頭にないので校舎は開いてたんです。確かに開いてました。とにかく「逃げろ!!」って言った時に、いろんな人たち集まっているから、もうズーズー弁だと何か思うんですね。不思議と。「逃げろ!!」と言うと「どこさ、逃げるの?」と聞くから、ああやっぱりそうだと思って。「校舎さ逃げろ!昇降口だ!!」って。それ聞いた知り合いの人たちがいて、すごい声大きかったんですって。校舎に逃げて1階と2階の踊り場の所に行ったら、がちゃがちゃがちゃとか「ぎゃあー」とかすでに聞こえましたね。本当に危機一髪だったんです。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
避難訓練も保育所の先生に言ったんですけど、避難訓練するからってお母さんたちそこで待っているし。そういう避難訓練じゃなくて、小野保育所だったのですが桜華小学校や未来中学校やこの辺の人と一緒に避難訓練が必要じゃないですかって言ったんです。早かったねでは評価に入らないと思います。先生達もいろんな先生いて、意識が高い人はうんと意識高いんですよ。自分たちはたまたまここにいて、あと移動するからいいの話じゃなくて、自分たち自身が今被災校にいるけど、どこか遊びに行って海で何あった山で何あったとかいう時もありますよね。子どもたちの心のケアだと言って、学校で楽しい行事をすごくやってくれるんだけども、楽しいだけでは駄目だし心のケアってとても難しいことですごく時間かかるんですけど、楽しい楽しいと言っても、例えばその時に5年後10年後に何かあった時にトラウマになる子たちって、どうしたらいいかってパニックになる子たちって多いと思うんですよ。だからこそ今「辛かったね、悲しかったね、怖かったね」というのを、みんなで心のふたを開けて語り合って「そうだったよね~」って。先生は経験してないでしょって言われたって、経験してなくても大人は分かり合えなければならないし。みんなで全部がそうできるかってそうじゃないんだけど、怖かったけど防災のためにどうしたらいいのかっていうのを、ちゃんとした授業の中で取り上げてもらわないと子どもたちどうしたらいいか。親だって怖くて話できないとか、どうしたらいいかわからない親がいたらその家庭では話できないことですよね。だから、学校で教育してもらってそれを家庭でもとか、大人たちも参加してもいいですよとやってもらわないと、あと何年後かに怖いなと思うんですけど。教育委員会だけじゃなくて、市全体としてね。過ぎたからじゃなくて、これからというのもあるし。そういうふうな思うことを、いろんな人を交えて話す機会があるといいと思います。いろんな人が言って、守るものが守られたらいいのかなと思ってます。
|
|
亀廼井 雅文(かめのい まさふみ) 50代 男性
白鬚神社 禰宜
(平成27年2月12日東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
当日は石巻で宮城県神社庁桃生支部の監査と役員会があり、私が事務局をしてましたので全部書類を整え出かける直前で、ちょっと時間があったのでコーヒーを入れて飲んでたんですね。その時に地震の揺れがありまして、もう歩けなく立てない状態でした。それなりに静まってきたのが1分ちょっと位過ぎたころですかね。部屋まで行ったらさらに揺れが強くなって、外に出れたのが2~3分後位です。一番びっくりしたのが揺れもそうなんですけど、もの凄い音がして2階の棟瓦が落ちてきたんです。バリバリバリっと、その音が一番印象的だったんですけども、それが家の前後ろに落ちたのもあるし突き破って風呂場に落ちてきたんです。神社も心配になったのでそのまま真っ直ぐ神社に行きました。神社は鳴瀬川の河口でしたので、もう避難は始まっていまして消防の人に「亀廼井さん、津波警報出てるよ」と言われ、無事を確認してすぐ家に戻ってきたんです。戻ってきたら、小学校の体育館が避難場所になっているのでその付近が少しずつ騒がしくなってきたんです。川向いの洲崎地区の区長さんが、早々と来て車の整理にあったたんです。「亀廼井さん、校門の所で車がつっかかって(渋滞して)いるからあそこで整理手伝ってもらえませんか?」と言われたんです。避難してくる方を誘導したんですね。20~30分そうやっているうちに悲鳴があがって、凄い音が聞こえてきたんです。バリバリって家が壊れる音。「うん?」と見たら、校門の真っすぐ前の道路の先にJRの踏切があるんですけど、そこに車を運んでくる津波が来たのが見えたんです。おそらく南から来た津波じゃなくて、東から来た津波ですから20~30メートル先まで来てたと思います。でも津波が見えたっていうのが一番よかったんですね。見えた瞬間に子どもの頃から「津波を見たら山に逃げろ」とばあちゃんに常に言われてたから、山に走ったんです。小学校の避難場所だった体育館の脇が崖になっているんですけども、その崖に生えている草にしがみ付きながら崖を登って行って上がったんです。その時ちょっとでも遅れればもう呑まれたと思います。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
どこでも何か起きるでしょうけど、海の近くということで津波だけは言い伝えていってほしいと思います。津波を甘く見ないようにといことですね。
あと、中央集権一極集中はやっぱり駄目だなと思います。これに即して再建を図っていきたいと、特に地元にあるものを活かして。野蒜で言えば、海です。そういうのを今後、この津波で捨ててしまわないでちゃんと海水浴場を安全な状況で作っていく、あと宮戸の奥松島も松島に負けないように。奥松島をよりディープに掘り下げていって縄文時代まで掘り下げれば、歴史的にこっちの方が完全に呼べるし。この辺は縄文深海の通りの風景をそのまま残しているんですから。海で言えば大きい遊覧船は無理だから、小さい島めぐりの船とか。ホテルに対しては民宿街を復活させていくとか、そういう感じの復興を自分なりに考えてはいます。どういう働きかけしていけるかはわかりませんが。
|
|
 |
宮崎 敏明 40代 男性
東松島市立宮戸小学校 教諭
宮戸小学校にて被災
(平成24年8月10日 宮戸小学校にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震発生時、子どもたちは1年生を除いて、まだ授業中でした。1年生は下校していました。揺れがおさまったところで児童を校庭に避難させました。保護者より、15時頃に津波が来るとの情報が入りました。保護者引渡しを考えていたのですが、その情報をもとに、とにかく帰さないということで教頭に確認をしました。それと前後し、続々と住民の方が押し寄せてきました。1年前に耐震工事をしていたので、体育館の方に移動することになりました。住民が車で続々押し寄せてきたのですが、約900名が本校に来ることになりました。
15時55分、校地下ののり面まで津波が押し寄せてきました。フェンスのところまでは100メートルくらいありましたが、もし校庭にまで水が来た場合は校舎に逃がさなくてはいけないと思いました。
1日目は食べ物がなかなか手に入らない状況でした。不幸中の幸いで震災当日、6年生が先生方への感謝の会を企画していまして、お菓子などを作ったものがいくつかあったんですね。子どもたちにはそのお菓子を食べて飢えをしのいでもらいました。これは本当によかったです。あのお菓子には本当に感謝でしたね。
次の日の朝、状況を確認しました。4つのうち3つの浜、大浜、月浜、室浜は壊滅状態。里浜については残っている家もあるけれど、もちろん完全に大丈夫だというわけではなく、床上浸水などという状況でした。島と野蒜とをつなぐ松ケ島橋は水没し、段差があるとのことでした。
12日、ひとつ残っている里浜から食料、燃料などをたくさん供給していただきました。宮戸では里浜のみなさんの協力で本当に助かりました。民宿もありますから毛布などもすべて提供していただきましたし、発電機もありました。本土と分断されて孤島となってしまった中でも、ひとつだけ残った浜からいろいろなものを提供してもらえたという面では、改めて常日頃からのコミュニティの大切さを感じました。
宮戸小についても防災マニュアルはありましたが、“帰さない”というマニュアルはありませんでした。しかし、海の仕事をしている保護者の方から津波が来ると聞き、そして逆にまわりの方がみんな宮戸小に逃げてきた。やはり海のことを知っている現地の方の情報をもとに、そのときの判断で避難できたことがよかったと思います。不幸な出来事ではあったのですが、宮戸地区の場合には日頃からのコミュニケーションが生きたケースだったのかなと思います。
4月21日に新学期がスタートすることになり、4月11日から20日までは自主学習期間を設けました。保護者と子どもたちにとって、学校が再開に向かっていることへの安心感を感じ取ることができたようです。4月10日までの校舎の明け渡しを確認し、全住民で清掃活動をしていただきました。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
たくさんの人がいる中で校庭の花壇の外側に水仙がひとつ咲いたんですね。それにものすごく心が揺さぶられましたね。つまり、芽が出た時点で約900人の方が行きかっていましたから、そんな中で、芽に気づいて誰も踏まなかったんですよね。少しずつ芽が大きくなって、ちゃんと花を咲かせた。花を咲かせられるという水仙の力強さもそうですが、それを踏まないで見守っている島の人たちの優しさを改めて感じましたね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
宮戸小学校では“宮戸島復興プロジェクトチルドレン”ということを行いました。子どもたちが夢や希望を持って学校生活を送るために、10年後の宮戸島を図工で表現しようではありませんか、ということでこのプロジェクトが始まりました。10年後の宮戸島の様子を思い、夢や希望をもって毎日の生活をがんばろうとする自分になれるようにということで取り組んでもらいました。全作品が出来上がり、夏休み中に校内展示をしました。108名に参加していただいて回答をいただいた結果、約70%の人に「子どもたちの絵から元気をもらった」「一人一人の個性が出ていてよかった」と言っていただけました。自分が元気になるというねらいも含め、家族が笑顔になるというねらいも達成されたなと思いました。
このように感じたあたたかい思いを親子による造形活動を行うことによって、一層、夢や希望に向かって歩み出させたいと思いました。子どもたちが望んでいる思いを、親が聞いてあげ、それを字に表しました。そしてこれは東京のデザイナー14名ほどによって、Tシャツにしていただきました。親子で一緒に作った文字も入っている。ということで、かけがえのない世界にただひとつのTシャツになりました。
各自の絵を児童自ら、同じテーマごとにグループを作ってひとつの壁画にしようということになりました。釣りができる宮戸になってほしい、お客さんがいっぱい来てくれる宮戸になってほしい、自然がいっぱいの宮戸になってほしい、夕日がきれいな宮戸になってほしい、など、だいたい6つの枠がありました。そのグループごとにさらに話しをし、こんな絵にしたいなということを模造紙に描いてもらいました。その6つできた絵を、さらに全員で話し合い、こんな宮戸にしたいというのをまとめました。
夢を夢で終わらせないためにということで、いま、ハマボウフウ、ハマヒルガオの再生に取り組んでいます。ハマヒルガオについては大浜に移植をしました。ハマヒルガオというのは小さな芽のうちから隣の芽と根をからませて、手と手をつなぎ合って海風、波に負けないようになるそうです。そうやって、手と手をとりあって強く生きてゆくんだね、みんなもそうなってねと、教えていただきました。花言葉は絆なんだそうです。まさに、今の子どもたちの取り組み、こうなってほしいなという願いが表れているなと思いました。ハマボウフウについては、根が地中深く、1メートル以上も伸びるんだそうです。そうやってしっかり根を張って、津波にも負けない強い人になってね、というお話もいただきました。夢や希望を持って、しっかりと根を張って、協力しあって島の再生に向かっていってほしいなと思いました。
子どもたちの夢や希望が、10年後、本当に高い志となって震災前以上の宮戸になってほしいなと思います。不幸な出来事、辛い出来事ではありましたが、それに負けないで頑張っている宮戸の子どもたちですし、そしてそれを支えているのは本当にすばらしい宮戸島のみなさんです。私も宮戸小学校に勤めていて、人間の生き方といいますか、生きるための心構えというか、そのようなものを学ばせてもらっています。これからも、みんなで頑張っていけたらいいなと思います。
|
|
鈴木 勝 40代 男性
宮戸島月浜にて民宿経営
石巻で買い物中に被災
(平成24年9月7日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
当日は石巻のイオンにいました。あの日はたしか金曜日で、私と妻とで土、日の民宿のお客さん用の買い出しに行っていたんです。地震の揺れがすごく、私は漁師の息子なので、“地震イコール津波”っていうのは小さいときから、私の親父、そのまた親父のおじいさんからも、チリ地震津波の経験とか聞いてました。これはすぐ帰んなきゃいけないってことで、裏道を使って帰りました。子どもたちの安否を確認するのに、一番最初に宮戸の小学校に行ったんです。その時、ちょうど雪がパラパラ降っていて消防団のジャンパーと、毛布を取りに自宅に戻ろうと思ったのです。
父は、うちにはバスがあるので、ラジオで女川に6メートルの津波が来たっていう情報聞いたみたいで、年配の人たちを小学校に避難させてたんです。じいさんは、バスで2回くらい運んだらしいんですけど、2回目のときに危ねぐ(なく)津波に巻き込まれそうになったそうです。
家に戻って、着いた途端10秒くらい後に波が来てしまって。裏にある民宿の2階に行ったんですけど、そこでもやばいということで、出窓に上ったんですよ。こんどは家の中に波が入って来て・・。これはまずいと思って、2階の雨どいをつかんだら、たまたま上れたんです。屋根に上げたんですよ。そしたら、もう、そこにいた場所もすぐに水没してしまって。2階の半分以上浸かったので、だいたい9メートルくらいですかね。それでたまたま、屋根の上で助かったんですよ。波が引いた瞬間、私たちがいた出窓に、どっかの丸太か何かが引っ掛かったんですよね。それも、こんな紙切れ一枚のようなべニヤ板に挟まって、架け橋のような感じで止まったんですよ。その上を降りて家の裏の五十鈴神社に逃げました。安全になってからみんなで小学校に移動しました。
小学校の体育館と、教室に避難したんですけども・・うちでは、ばあちゃんと娘を小学校に置いて、親父と私たち夫婦と息子2人は、寝るときはワゴン車で寝ました。約1ヶ月くらいは小学校にいたと思いますね。その後は宮戸の里浜にある漁協の倉庫に、月浜の約60人で雑魚寝ですね。仮設ができるまで、2~3ヶ月くらいはいたのかなぁ。
宮戸島の被害は、大浜と月浜は外洋なんで、一番壊滅的にやられているんですよ。うちら方の、月浜は残るっていう人はいるんですけど、大浜がだいぶいなくなるみたいですね。室浜もけっこういなくなっているのが多いみたいですけど・・。たぶん一番残るのが月浜だと思うんですよね。
今の仕事は漁師よりトラックの運転が昔から夢だったんですよ。だから今はもう、自分のやりたいことプラス、いろんな仕事ができるから楽しくてしょうがないですね。現場の人たちもみんないい人たちで。やりがいはあるんですよね。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
今までいろんなボランティアの人たちが来てくれて。奈良県の大和郡山市に家族5人で招待されたんですよ。宮戸のお祭りのときに、金魚すくい大会があって、長男が52匹すくって、優勝したんです。それで全国大会に出させてもらって、大変でしたね。カメラがずっと金魚のふんみたいに付きっぱなしで。今でも大和郡山の人たちと交流があって、宮戸のお祭りって言えば来てくれるんですよ。子どもたちも友達になったし、お父さんたちとも友達になってね。招待してもらったときは、ちょうど組合の倉庫にいたときだったんですよ。気晴らしというか気分転換になりましたね。全国金魚すくい大会っていうのがあるんですけど、会長さんが、金魚を送ってくれたんですよ。もし、また東松島で金魚すくいやりたいって言えば、喜んでバックアップするからっていう話なんですよね。
やっぱり、残っている人たちで、今までどおりにはいかないと思うんですけど、昔のように、みんなで楽しく暮らせるような地域にしたいんですけどね。震災がなければ・・って思ってもやっぱり、自然災害だからね。またいろんなお客さんたちが来られるように、復興することですかね。前向きに進んで行くしかないように思いますね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
これからは、私たちの代でなくて子どもたちの代ですからね。“えんずのわり”もこのままずっとね・・。下にもやろっこ(男の子)がいるから、3人のうち2人じゃないですか。
“えんずのわり”は俺の代でこれ、潰してられねぇなっていうプレッシャーがあったみたいですよ。
震災を機に、子どもたちはずいぶん変わりましたよ。私がいない時なんかは、海苔仕事する時には、船に行って自分で進んでやっていたしね。海が好きみたいですね。特に長男なんかは、じいさん、ばあさんと一緒に住まないと嫌だって言うんですよね。やっぱり生まれた時から一緒に住んでいるから。とにかく俺は宮戸からは絶対出ないからって。やっぱり自分は生まれ育った宮戸にいたいっていうのがあるんでしょうね。
|
|
山内 良裕 50代 男性
奥松島海苔生産グループ「月光」代表
(平成25年8月9日 宮戸 奥松島海苔生産グループ月光にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は、夜明け前に海苔を摘んで来て、海苔の生産作業をやっていました。朝前に海苔を摘んでくるんだけれど、朝前だけだと早く終わってしまうので、午前中に機械を回してから、もう1回摘みに行って、それから協同作業っていうか準備作業に出ました。それが終わって3時頃、組合で慰労会をやろうとした途端に、コップに手をかけたら地震が起きた。最初「地震だ」って言っていたんだけど、すぐに大きくなってね。これでは駄目だと思って。2階にいたので、階段から降りてくるのもなかなか大変でした。
家族は9人いたんだけども、そのうち、下の息子は仕事に行っていました。息子の嫁さんは、確定申告に行っていたんだね、石巻まで。連絡はすぐについたみたいなんだけども。終わって矢本で買い物をしていて、そのまま帰って来たんだけども、途中で津波なんか来たら、そこでおしゃかだった(だめになっていた)んだね。津波が来る前に着いたから、危機一髪だったっていうか、安心したんだけどね。家族が、何をしたらいいのかわかんないような感じで、立っていたんだね。すぐに、「車に乗って、高台に避難しろ」と言って、避難させて。
その後が俺の馬鹿なところで、俺と息子は必要なものを取りに行ってこよう、ってことで(家に戻りました)。ちょうどガソリンの買い置きがあったので、100リッタードラム2本、ガソリンと発電機だけは軽トラに積んで、また高台に避難しました。その時は軽トラのラジオはつけっぱなしでした。その時に「女川に6メートルの津波が来た」とラジオの放送があったのね。高台の方に戻っていこうとしたら、まだ下で区長さんは「津波が来ますから、避難して下さい」と防災無線で話していたんだね。一生懸命に話していたんだけど、とにかく女川に(津波が)来たから、「こっちも必ず来っから(来るから)早く逃げた方がいいよ、もう誰もいないからわ(いないから)」ということを伝えて、逃げて避難してもらったんだ。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
みんなありがたいんだけども、3週間くらいつながらなかった道路がつながってすぐ、山形からわざわざ車でガソリン20リットルたがえて(持って)来てくれたんだね。何を言うのかと思ったら「山形まで一緒に行きましょう」と。「何とか、食べるものとか泊まる所はあるから。とにかくここでは大変だから、何もないから。山形まで一緒に行って、避難生活したらどうですか」と言われたんです。その気持ちがね。
そういう人が結構いました。親戚にも、「塩釜の方で、1軒空きがあっから(あるから)、そこに避難したらどうだ」って言われたんだけど、ここを離れる気持ちはなかったね。流されたっていっても、月浜はわりと山の方に家が押し込められたので、やっぱり瓦礫の中には、自分の物もあるので、そういう物も探さなきゃならないし。離れる気持ちはなかったです。
|
|
門馬 善道 60代 男性
語り部ガイド
(平成26年2月25日東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
私は地震が来て落ち着いた段階で、(石巻市立病院の)窓辺で日和大橋を見てました。(津波が来る)30分前位から引き潮が始まってました。市の広報車がずっと海の方に向かって行って、その車がまともに波に流されるのから、津波が道路を越えて来るのを全部頭からっぽの状態で見てました。日和大橋から、日本製紙の方に行く道路を一気に越えて来る津波は凄かったです。私の車も浮いて川に流されるまで、ずっと見てました。景色が変わったのは、第1波がきて5分くらいの間ですね。5分くらいで1回目の波が北上川にだあーっと行って流されたと思っていたら、門脇小学校から日和山に行った波が戻って来るのに、住宅が全部流されて文化センターと病院の間、病院の駐車場で渦を巻いて2回転くらいするんですよね。
真っ暗闇になる前後から門脇小学校の火と煙が見えたんです。真っ暗になる段階では、もう門脇小学校が燃えて真赤になっているのが見えたし、日本製紙の1カ所から高い煙が出て、南浜町と3か所くらいで煙が出てました。あと、多賀城の石油コンビナートは遠いけど夜中じゅう真っ赤になって見えてました。学校の火は恐ろしかったです。こげ臭いにおいがしてました。
12日の午後あたりに、計量コップで10CCずつの水分と、ラップにくるんだアルファ米を渡されました。整形外科あたりに入院していた年配のおばちゃんたちが、「お菓子をここにいる人達に配って」と持ってきました。それで少し何とかなるなって感じにはなりました。女川から歩いて来たという人から、女川・渡波が「ものすごい」っていう情報が伝わってきて、2次的なショックを受けました。ラジオの情報で山元町とかのラジオ発信は多かったんですけども、東松島市とか石巻の情報は比較的少なかったんですよね。福島の原発のニュースがどんどん流れたために、地元の情報は入らなかったですね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
人と挨拶する時、「おはよう。こんにちは」ですれ違うんだけど、私らの場合はもう一歩踏み込んで「このごろ変わりない?」って声をかけます。それが必要だから、それは心がけているの。「何か寒かったね、今年の冬。体調崩さなかった?大丈夫」っていうようなニュアンス、態度、それは私個人ではうんと気をつけいるんです。
牡蠣小屋もあくまでもアルバイトだけど、県外から被災を見ながら来る人が多いです。多いのが山形、福島、栃木、遠くは関西方面。その中には奥松島に、20年前に来たとか10年前に来たとか民宿に子ども連れて何回も泊りに来たとか、昨年はそういう人たちがだいぶ来ました。「おじちゃん、この松の木枯れてるけどどうしたの?」「こここんなに草生えているけど、津波でやられたの」と聞かれるので、仕事しながら「あそこに見えるのは野蒜海岸だよ。松の木ちらちらあるのは、本当はこういう状態だったよ。あそこにあるのは、かんぽの宿だよ」と説明しています。生の声を聴きたいからってわざわざ遠くから来ているんだから、牡蠣小屋の経営者には、牡蠣を売って儲ける事よりも、支援のお礼かたがたそれも含めて商売しなくては駄目だと言っているんです。高台の工事に来ている人も食事に来るから、このおじちゃん北海道から工事に来ているから喋りなさいとか、小屋の中をそういう雰囲気にしてます。
|
|
木島 新一 60代 男性
語り部ガイド
(平成26年7月31日自宅付近にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
地震の時は、私と女房はたまたま家にいたんだ。家は高台にあって避難所になっているので、いつも水なんかはタンクに確保しているんだけども、1か月ほど前にも地震があったので、うちの女房が気をきかせてその水を捨てて、ポリ缶を干してたんだな。そんで、地震きてはっと思って、女房はポリ缶持ってうちは高台で水が出なくなってたから、下の方はまだ水出るかなと思って、隣近所を避難を呼びかけながら水を貰いながら行ったんだけど、下の方も水は出なくなってたので「大丈夫ですか?避難して下さい」と話したらしいのね。俺は「ああ、これは津波来るな」と思いラジオでも津波(がくる)と言ってたから、うちでも危ないと思ったので、後ろの山に登って、草刈機械で草刈って通路作ったんだ。ちょうど岩を切って風除けになる所があったので、そこにブルーシートなど運んだんだな。うちの女房は「絶対、ここまで来ませんよ」と言ってたけど「いや、わかんないからすぐ逃げろ」と。何か家の中探して、持ち出そうとしてたけど「そんなものいいから、とにかく逃げろ」と逃げたんだけどね。
みんなも、ぬれ鼠になって逃げてきたんだけど、家でも危ないから、山の上まで荷物運んで、ストーブとか毛布とか運んだんだ。運び上げてちょっと安心したんだけど、雪が降ってきて寒かったね。その日の夕方水がなかったので、雪を集めてお粥にて食べたな。米はいっぱいあったし、魚とかは冷蔵庫にあったから心配なかったんだけど。水だけは心配で、雪降ったけど次の日は晴れるなと思って、雨どいを少しずつずらして、そこに樽とかバケツ置いて溶けたら水溜まるようにして。雨どいにタオルを二重三重にぐるぐる巻きにして、漉して飲み水をとったんだ。でも、小さい子どもさんの分はペットボトル1本しかなかったのさ、だけど漉した水飲ませるのも心配だったんだね。その時、家には私含めて10人いたんだね。
その後、ヘリコプターが頻繁に飛んでいたんだけど、自然の家(宮城県松島自然の家/野蒜字洲崎)の職員が次の日か当日かはわからないけど、電話で喋っているのをラジオで聞いたら「宮戸は壊滅だ」と言ってたから、残っているのは俺たちしかいないと思ってね。あの時はすごく不安だったけどね。子どもさんが3日目には病院に行かなきゃないということで、大きなコンパネがあったので赤ペンとペンキで「SOS、子ども病気」と書いて屋根に上げたんだ。「おーい」という声が聞こえたら誰かと思ったら里浜の消防団が、堤防の所が壊れていて家の前まで船で来て、迎えに来てくれたんだっちゃ。俺と女房と若い人3人残って、あとはみんな行ってね。そのお子さんは、すぐヘリに乗って搬送され助かったんだ。俺もあとから宮戸小学校まで行ったんだ。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
宮戸は、ウォーキングトレイルと言って、宮戸全体みんな遊歩道になってどこでも歩けるようになっていたんだ。その道も年に2回位草刈りしてるわけだ。やっぱりその道路があったのが、一番よかったし。あとは、ずっと昔から同じ人が住んでいるから、言い伝えを守っているんだな。この地蔵様から、右に逃げなさいとか左に逃げたら必ず犠牲になるよとかってあったから助かったし。あとは、室浜と観音寺を結ぶ道路とかあって、その道路もお盆になるとご先祖様がこの道を歩ってくるからと言って、今でも年に1回くらいは草刈しているみたいなのね。だから、いつも語り部で言うのは、いろいろ小高い山とか丘とかあったけども、そこはほとんど利用されてなかった。やっぱり山に登る道はつけておくべきだと、俺は話しているんだけども。そういうことで、宮戸と野蒜の犠牲者数の明暗が、分かれたのかなと俺は思うと話しているんだ。自分たちはどこに逃げるんだか、常に頭に入れておかなきゃないと話してんだけどさ。
|
|
 |
菊池 祐子 30代 女性
東名・野蒜の情報誌“てくてく通信”を発行/福祉施設勤務
平成23年3月11日 和歌山県高野山での修業中に震災を知る。
(平成24年9月11日 東松島市図書館にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
3月11日は和歌山県高野山で修業をしていまして、慌ててテレビの方に行ったら、リアルタイムで名取市のすごい濁流が映っていて、「これは・・なんだ?」と思ってびっくりしました。
4月から東松島市の東名の“すみちゃんの家”という高齢者施設に勤めるということで約束していたんです。その代表のところがどうなっているのかなって思って、何回も電話したのですが、つながらなくって・・。帰りたいっていう気持ちが強くなって、3月24日に山形経由で、山形からは高速バスで戻って来たんです。やっと塩釜の自宅に戻ってきて、代表と電話連絡が取れたんです。なんとか小野とか野蒜の方に入って、そこで一緒にボランティアというような形で入ったんです。
すみちゃんの家は仙石線の東名駅の近くだったので、建物自体は残ったのですが、1階は全部だめで泥だらけでした。二階は大丈夫だったので、代表と、所長と一緒に、二階に泊まって復興作業をしましょうということで、こつこつと作業を始めました。
7月7日にそこでデイサービスを始めました。ようやく再開復興みたいな感じで、やっとそこだけきれいになって。ひたすら泥かきの4ヶ月でしたね。お泊りする方もスタッフの方も戻ってきて、なんとか再建という形ですね。ゆくゆくは高台の方への移転を考えているみたいです。
|
|
|
|
| 感謝のメッセージ |
|
|
いま、“てくてく通信”を作っているんですよ。なんとか野蒜を元のように・・野蒜に住んでいた人たちが少しでも戻ってくるようになったらいいなっていう思いが一番あります。
いろいろ調べて、みなさんに発信すれば、仙石線も動くかもしれないし、とにかく、何かそういう声とか状況を伝えれば、いい方向に変わるんじゃないかなっていうのがきっかけでやってます。東名、野蒜の方だけじゃなくて、外部の人にも伝えたくて、月に1回発行してます。なんとか仙石線が戻ってきて、東名と野蒜の町が元気になればいいなって思います。それを続けていけば何かが変わるかな、思いがつながるかなっていうのが今の思いですね。
野蒜の海の方を見れば、建物がまだ水に浸かっていたりとか・・。自分は亡くなった方のことを忘れないように、供養し続けることが義務なのかなって。思いをつないでいくことが、自分の使命なのかなって、今考えていて・・。それが、お寺っていう形なのか、ちょっとよくわからないんですけど、とにかく心のよりどころになるものを作りたいなって思っています。忘れないでいることが供養になるのかなって思います。
亡くなった方が応援してくれているから、その分、私たちも頑張らなきゃないんだって思いますね。亡くなった方の思いを無駄にできないなっていうのは、すごく思っていて、それを伝えていかなきゃいけないなって・・。
知り合いの尼さんが、「あなたが行くところがお寺になればいいんじゃないの」って。どこかに行って、写経の会をして、そこがお寺になればいいし、何かお話し会をしてそこがお寺になればいいし。そこに行って供養したところがお寺さんであればいいのかなって。最近はそういうスタンスで考えていますね。
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
この前、富士山に行ってきたんですよ。いま、夢ハンカチっていう、ハンカチに夢を書いて富士山に揚げようっていうイベントがあって、それに参加しまして。夢を持つことで人は元気になれるっていうか、そういうことを今考えていて・・。わたしの師匠、教えて下さっている住職が言うには、どんなに食べ物があっても人は生きていけないと。夢とか希望がないと生きていけないと言っていて。夢ハンカチというイベントを企画している方も、夢がないと人は死んでしまうっていう話をしていて・・。みんなで夢を持てたらいいなって、震災で傷ついて夢が見つけられない、希望が見えないっていう方たちも、元気になるために夢を持てたらいいなって。今、そんなことを考えている感じです。
うちの母は縫いものをして、何かをつないでいくことが私ができることだって夢守袋を作っています。全国各地の人が震災のことを忘れないで、つないでいってほしいなって思って。
|
|
石巻日日新聞社のみなさん
(平成27年3月26日石巻日日新聞にて取材)
|
|
|
| 被災体験談 |
|
|
外処 健一
40代 男性
東松島市赤井
|
|
あの時は報道部のミーティングがありまして、私は(石巻)市役所にいたんですけどそこから戻って会社(石巻市双葉町)に帰ってきました。みんなで集まってミーティングをしようかなと思っていた矢先にあの大きな揺れが来たんです。揺れが治まって各担当者がそれぞれ海の方、あるいは担当行政区の方に散り散りになりました。私も市役所に行ったんですけど、向う途中まだ道路は空いていたんですが信号機がガタガタ揺れたりとか、車に乗っていても電車に乗っているような感じだったんです。道路が真っすぐ走れないと言うか。役所に着くと、雨漏りがして職員が対応に追われていて、その時はまだ津波が来るいう予見が全くできてませんでしたので、ほとんどの方が宮城県沖地震来たねという会話をしてたんです。そうこうしている間に、浜の海の匂い潮の匂いがだんだん漂ってきまして、窓の外を見るとじわじわと水が市役所の周りを囲むようにして入って来ました。もうみるみるうちに1メートル近く上がっていきました。いろいろ情報が錯綜してまして、我々としては市内がどれだけの被害なのか全然把握できなかったということもありました。黒板に役所の職員が書いているのをこちらもメモして、会社があるのか残っているのか残っていないのかそれすらもわからない状況でした。
|
平井 美智子
50代 女性
東松島市矢本
|
|
その日の新聞の印刷が終わって、3時からミーティングというちょっとした空いた時間だったので、翌日の紙面で作っておけるものってことで土曜日の紙面作りを、報道部の隣りに編集制作の部屋があるのでそこで担当者とパソコンを見ながらやってた時に揺れ始めたんです。初めからけっこう大きな揺れだったんですけど、いつまでも止まらなくてすぐ机の下に体を入れたんだけども3分以上の揺れだったので、過去の地震とは比べ物にならないくらいの規模の地震だととても恐ろしくなりました。すぐ報道部の部屋に戻ってみんなに指示して、それぞれ担当の場所に警察・消防の担当はそちらの情報だとか。記者になって30年ですけど石巻で地震が起きたら必ず津波が来るものということが前提だったので、私は現場じゃなかったんですけど、今回は津波が来る恐れがあるのでカメラを構えてということを指示したんです。人によっては、日和山の方に行ったり北上川の河口の方に行った者もいたんですけど。私自身は、とりあえず日和山から取材しようと思って山頂の方でカメラを持って待ち構えていました。 30分したら、日和山の上の方で雪で景色が見えなくなってきた時にみんなが大騒ぎ始めたんです。指を指している方を見てみると津波が襲ってきていました。今度はぱちぱちと凄い音がして見たら火が出始めていて、あちこちで車のクラクッションのすごい音がしてたり燃える音とかして、もの凄い事が山の下で起きていました。
|
熊谷 利勝
30代 男性
石巻市和渕
|
|
私は当時も東松島担当でした。議会が最終日だったので(東松島)市役所の方へ取材に行きました。議会が閉会し議会事務局で取材してまして、その時に揺れが来て部屋の中はしっちゃかめっちゃかのような感じで机の下にもぐりながら、ロッカーを必死で押さえてたのを記憶してます。何とかその揺れが治まって、カメラがあったので庁舎内のいろんな物が散雑に散らばっている様子を写真を撮って、防災課に行きました。防災課だけ電源があってテレビがやってたので、そこで津波が来るという話は聞いて、震度は6強だったと思います。そんな情報を集めている最中に庁舎内から退去してくれという指示が出たので、車で矢本西小学校に行ったんです。その後は信号がその時もうついてなかったので(国道)45号線方面が渋滞してたので、西から東へ行くような感じでヨークベニマル(矢本店)の前あたりを通ったんです。
そういった中で車はどんどん海岸の方に行ってしまったんですね。取材しながら会社に戻ろうという考えで、途中で大曲市民センターに行って大曲浜の方から避難してくる人の様子を取材したりしてました。あとから写真を見た時その時は3時40分くらいで、でもまだ大曲市民センターの雰囲気はそれほど緊迫した感じはなかったです。あの時も避難してきた人は情報を持ってないんですね。警報が鳴っているというのも津波が来るっていうことも知らなかったようです。その時、大曲市民センターの脇の通りは北側に向かってかなり車が渋滞していたんですね。でも南側は空いてたんですよ。避難して来た人も南側は空いているから石巻方面は行けるっていう話はしていたので、それを間に受けて市民センターから南の方に行って左折して東の方面に定川橋の方ですが、進めて行ったところ橋の途中で道路が途切れていてひび割れて行けないような状態で通れなかったんです。路方に車を止めて、定川橋の上にハザードランプをつけた大型のトラックの写真を収めようと思って、数メートルほど小走りで走ったところで目の前に、前の方からさあっと水が来たんですね。
「これは津波だ」と思いまして、反転して一番最初に目に入った一番高い物、会社の前の門扉ゲートだったんですけどそれに走って行ってよじ登って、みるみる流れが強くなっていって同時に嵩も増していって、けっこう門扉と自分が上がった所と合わせても2メートル位はあったと思うんですけど、そのゲートの上に登ってですら腰くらいまで水が来てしまい「これはまずいな」と。その時にちょうどプラスチックの青い色の魚を入れるような箱がうまいぐあいに流れてきたので、それを手を伸ばして捕まえて浮輪代わりにして、覚悟を決めて流されようと。引き波になったところで浜の方から流されてきた船が横倒しのまま田んぼのど真ん中でちょうど止まってたんです。そこにうまくたどり着けたんでよじ登りました。
そうこうしているうちに日が暮れました。私がいる周りはほぼ静寂でした。間もなく石巻方面から真っすぐ私の方に向かって来るヘリがあったので、手を振ったらふっと行ってしまって。そしたらぐるっと旋回して脇に来たんです。「あっ、よかった」と思って。上から消防隊員のような方が降りてきて、自分の体にベルトを巻いてぐうんっと。一瞬ですね。真上から船とその周りの波紋みたいのが見えて、だんだん船が小さくなっているところまで覚えています。あとは機内に入ってそこから記憶がないんです。
|
|
|
|
|
|
|
| 未来に向けて |
|
|
外処 健一
|
|
(質問)震災を経て、これからの紙面作りにおける意気込みをお聞かせください。
この災害で一つの力を身につけたんじゃないかなと思います。というのは災害をイメージできる力。これがたぶんこの地域の方は備わったと思います。阪神大震災がもしここで起きた場合、どのくらいの規模にあたるのか全然想像つかなかった。ただ今回大震災を経験したことによって、同じような災害が起きた時にこの地域は一体どうなるのかというものが、皆さん実体験でわかっています。
これからやっていかなくてはならないことは、災害が起きたらこうなるよというもの(イメージ)を忘れずに未来に発信していけるかということなんです。よく風化と言われますけど、風化はどこから始まるのかというと、関東でもなく関西でもないし海外でもないんです。ここから風化というのが始まるんです。我々が伝えることを止めてしまう、もしくは伝えなきゃならないことを伝えなければ皆さんの記憶というのはどんどん消えてしまう。だから風化という言葉がないような状況にしたいと思いますし、被災した我々も同じような災害で同じ悲しみを繰り返さないようにするためにもイメージできる力をどんどん広めていかなければならないと思います。
|
|
平井 美智子
|
|
(質問)震災を経て、これからの紙面作りにおける意気込みをお聞かせください。
一言で言うと信頼ですね。世の中いろんな情報が出回っていますし、確かな情報、ためになる情報もあるんですけど、やはり日日新聞が書いているから間違いがないと、これからも地域の皆さんが思ってくれるような情報を続けて出していって、私の時代の次の世代の記者たちが動いている時も、それがDNAとして続いてくれればいいなと思っております。
|
|
熊谷 利勝
|
|
(質問)震災を経て、これからの紙面作りにおける意気込みをお聞かせください。
地域と共に歩んでいきたいと思います。
|
|
|
 |
東松島市教育委員会 東松島市図書館
ICT地域の絆保存プロジェクト
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜1-1
TEL 0225-82-1120 FAX 0225-82-1121 |